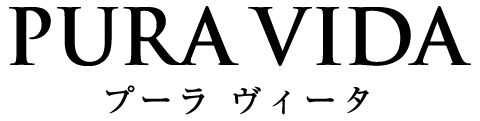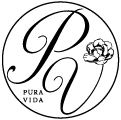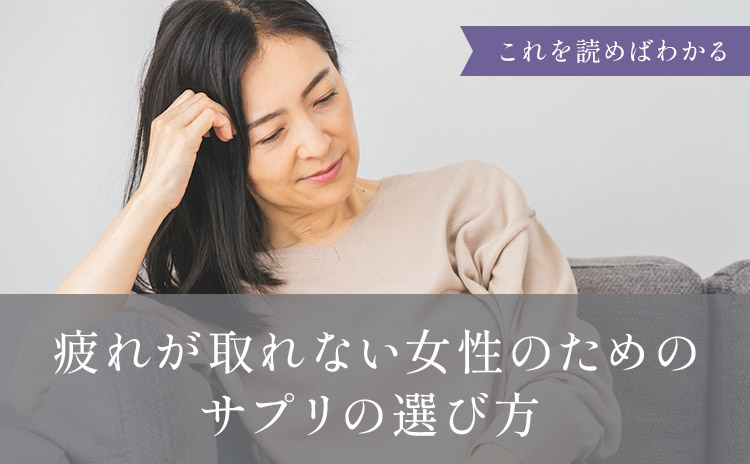「最近すぐにバテてしまって仕事や家事がきつい」
「睡眠を取っても翌朝に疲れが残っている」
「年齢とともに体力が落ちた気がして不安」
このような悩みを抱えていませんか?
体力を回復させるには、ただ休むだけでは不十分です。栄養バランスや生活習慣など、総合的な見直しを行うことで、元気を取り戻し、活き活きと活動できるようになります。
今回の記事では、以下の内容について詳しく解説します。
| この記事でわかること |
|
日々のパフォーマンスを高めたい方は、ぜひチェックしてみてください。
体力回復には、質の高い睡眠(6〜8時間)と栄養バランスの見直しが必須です。特にタンパク質、ビタミンB群、糖質を摂取し、軽度な有酸素運動や腸活で心身を整えます。寝だめ、食事抜き、栄養ドリンクへの過度な依存は、回復を妨げるため避けてください。
目次
体力が回復しない5つの理由
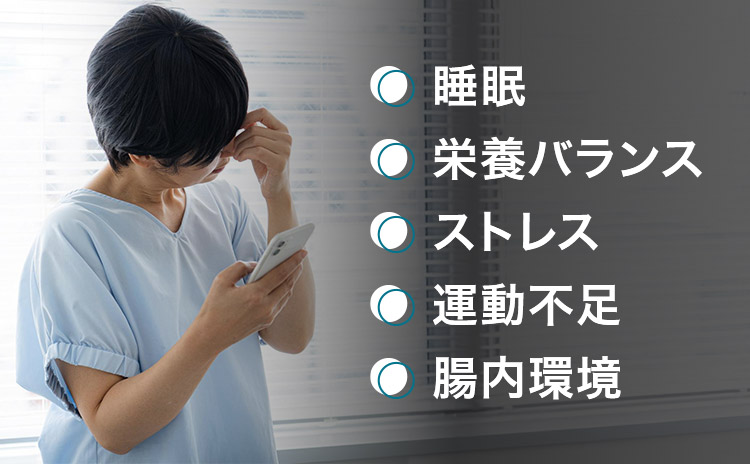
体力が回復しない5つの理由として、以下が挙げられます。
- 睡眠時間が足りていない、睡眠の質が低い
- 栄養バランスが悪い
- ストレスが溜まっている
- 運動不足に陥っている
- 腸内環境が悪い
自分に当てはまる部分がないか、セルフチェックしてみましょう。
1-1. 睡眠時間が足りていない、睡眠の質が低い
厚生労働省の調査によると成人に必要な睡眠時間は目安として6~9時間とされており、これを満たさないと疲労物質が蓄積されやすくなります。疲労物質が溜まることで体が常にだるく感じられ、集中力の低下を引き起こします。
また、睡眠時間が十分でも、「途中で目が覚める回数が多い」「熟睡感が少ない」など、睡眠の質が悪い状態が続いていると、体力の回復が思うように進みません。
睡眠不足や質の悪さが慢性化すると、仕事や日常生活にも支障が出るため、十分な睡眠時間を確保することが重要です。
1-2. 栄養バランスが悪い
栄養バランスの乱れも、体力回復を妨げる要因の1つです。
例えば、筋肉再生や疲労回復に必要なタンパク質が不足すれば、体の回復が遅れてしまいます。また、炭水化物に偏った食事では、一時的なエネルギーしか供給されず、すぐに疲れやすくなるでしょう。
加えて、野菜不足によりビタミンやミネラルが不足すると代謝が低下し、ますます疲れが抜けなくなります。
自分が不足している栄養素を見直し、バランスよく摂取する習慣を意識しましょう。
1-3. ストレスが溜まっている
慢性的なストレスが長期間続くとホルモンバランスが乱れ、睡眠の質や食欲にも悪影響を及ぼします。
特に仕事などで日常的にイライラが溜まっている場合は、意識的にストレス解消の習慣を取り入れることが必要です。趣味や軽い運動、リラックスできる時間を設け、心身を安定させましょう。
忙しい場合でも、ストレスを発散させる時間を設けることを意識してみてください。
1-4. 運動不足に陥っている
日常的に体を動かさないと血流が悪くなり、全身に酸素や栄養が届きにくくなります。その結果、筋肉が衰えることで基礎代謝が低下し、疲れやすい体になってしまいます。
階段の上り下りやちょっとした動作でも疲れやすくなり、より日常生活がつらくなるはずです。
対策として、ジョギングやサイクリングなど簡単に始められる運動を習慣化し、運動不足を1日でも早く解消しましょう。
1-5. 腸内環境が悪い
体力を回復させたい場合、腸内環境を整えるのも重要です。腸内細菌のバランスが乱れると、栄養素の吸収効率が落ち、体力低下につながります。
腸は「第2の脳」とも呼ばれ、腸内環境が悪化すると全身のエネルギー生成や健康維持に支障をきたします。
| 参考: | 腸内フローラ 腸内環境 免疫機能-日本健診財団 |
さらに、腸の状態が悪いと体力だけでなく、美容面にも悪影響が出ることがあります。
キムチやみそ、納豆などの発酵食品を積極的に摂取し、腸内環境を整えましょう。
腸内環境が悪いときに現れる5つの症状!原因や整えるための改善策も紹介 >>
体力を回復させる5つの方法

体力を回復させる5つの方法として、以下をご紹介します。
- 質の高い睡眠を取る
- 栄養バランスの良い食事を心がける
- ストレス発散を行う
- 軽度の有酸素運動を続ける
- 腸活を始める
再現しやすい内容なので、ぜひチャレンジしてみてください。
2-1. 質の高い睡眠を取る
家事や仕事で忙しい場合でも、なるべく6時間~8時間の睡眠をとる習慣を作りましょう。睡眠は疲労回復に大きく関係するので、優先して時間を確保する必要があります。
また、睡眠の質を高めることも重要です。就寝前1時間はスマートフォンの操作やテレビ視聴を避け、入浴やストレッチを行うと、ぐっすり眠れるようになるでしょう。
知っているようで知らない「睡眠の質」の重要性。睡眠の質を上げる秘訣を専門家が解説 >>
2-2. 栄養バランスの良い食事を心がける
普段の食事の中でタンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取しましょう。
特にタンパク質は筋肉の修復に必須で、疲労回復にも関わる栄養素です。体重(kg)×1.0~2.0gを目安として肉、魚、卵、大豆製品などから摂取することが大切です。
例:体重50kgの場合:50g~100g
また、抗酸化作用のある野菜や果物も積極的に摂り、さらなる体力回復につなげるとさらに効果を実感できます。
2-3. ストレス発散を行う
ストレスは体力を奪う大きな要因なので、定期的に発散する必要があります。
落ち着ける時間や、アクティブな時間を作ることで心身のリフレッシュになるでしょう。
例えばすぐにストレスを発散するための方法として、趣味、友人との会話、スポーツなどが挙げられます。
趣味やスポーツに費やす時間がない場合は、ストレッチや瞑想などの試しやすいもので、ストレスを発散してみてください。
2-4. 軽度の有酸素運動を続ける
ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動は、体力向上に効果的です。
毎日30分程度の運動を継続することで、心肺機能が強化され、疲れにくい体を作りやすくなります。
運動初心者の場合は、いきなり激しい運動をするのではなく、徐々に強度を上げるのがおすすめです。無理に強度の高い運動から始めてしまうと、体に対してダメージを負ったり、運動する習慣が続かなくなったりしてしまいます。
以下の有酸素運動は初心者でも取り組みやすく、続けやすいので、ぜひ参考にしてみてください。
| 運動の種類 | メリット |
| ウォーキング |
|
| ジョギング |
|
| 水泳 |
|
2-5. 腸活を始める
腸内環境を整えることは、エネルギーの産生や免疫力向上につながります。
発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)を毎日の食事に取り入れることで、腸内活動の向上を実現しやすくなるでしょう。
また、食物繊維が豊富な野菜、果物、全粒穀物は腸内細菌の餌になり、さらに腸内環境の改善につながりやすくなります。
詳しい腸活のやり方は、以下の記事で解説しているので参考にしてみてください。
正しい腸活のやり方5ステップ!続けるコツや食事メニューも解説 >>
体力回復に必要な3つの栄養素

体力回復に必要な3つの栄養素として、主に以下が挙げられます。
- ビタミンB群
- タンパク質
- 糖質
それぞれの栄養素を摂るべき理由について、詳しく見ていきましょう。
3-1. ビタミンB群
ビタミンB群は、糖質をエネルギーに変える役割を持っており、代謝を助ける重要な栄養素です。特に肉や魚などの動物性食品に豊富に含まれています。
ビタミンB群の中でも「ビタミンB1」は、炭水化物の代謝を促し、効率的にエネルギーへと変換するため疲労回復効果が期待できます。
ビタミンB群が不足すると、体内に疲労物質である乳酸が蓄積して体が疲れやすくなるため、積極的に摂取することが重要です。
3-2. タンパク質
タンパク質は筋肉や細胞を修復し、体を作るために欠かせない栄養素です。
| 参考: | 身体と心の疲労回復-国立研究開発法人理化学研究所 |
タンパク質は、肉、魚介類、卵、大豆製品、乳製品に豊富に含まれていて、これらを日々の食事にバランス良く取り入れることが不可欠です。
タンパク質が不足するとスタミナ切れを起こしやすくなり、疲労感が増します。
もし、日々の食事だけでは十分に摂取することが難しい場合には、間食としてプロテインバーやナッツを取り入れるなど、積極的にタンパク質を補給しましょう。
3-3. 糖質
糖質は身体を動かすための主要なエネルギー源であり、不足すると日々の活動のパフォーマンスが落ちてしまいます。
主に白米やパン、麺類などの主食に豊富に含まれているので、ダイエットをしている場合でも極端に糖質を制限するのではなく、食物繊維が豊富な玄米や全粒粉パンを選ぶなど、摂取方法を工夫するようにしましょう。
糖質はエネルギー源として大切な栄養素である一方で、摂りすぎると糖尿病など生活習慣病のリスクを高めるため、適量を心がける必要があります。
炭水化物中心の食事ではなく、タンパク質やビタミンを含む食べ物もバランスよくメニューに組み込みましょう。
体力回復における3つのNG行動

体力回復における代表的なNG行動として、以下があります。
- 寝だめをする
- 栄養ドリンクに頼る
- 食事を抜く
1つでも当てはまっている場合は、今日から改善しましょう。
4-1. 寝だめをする
睡眠不足を平日に溜め込み、週末に一気に寝だめする習慣は、体力回復において逆効果です。
寝だめをしてしまうと、疲労回復に必要なホルモン分泌が十分に行われず、疲労物質が残りやすくなります。
また、寝だめは体内時計を乱すため、週明けに倦怠感や頭重感が残ることがあります。
毎日一定の睡眠リズムを保った方が疲れが溜まりにくくなるので、日常生活において意識してみましょう。
4-2. 栄養ドリンクに頼る
疲れたときに栄養ドリンクに頼る方もいますが、逆効果になりかねません。
ドリンクに含まれる糖分やカフェインは一時的な覚醒をもたらしますが、習慣化すると体にさまざまな悪い影響を与えることもあります。
また、肝臓に負担をかけ、体内の解毒機能を弱める可能性があり、実際、米国フロリダ州では、毎日4~5本の栄養ドリンクを3週間飲み続けた男性が重度の肝機能障害で入院した事例もあります。
栄養ドリンクは短期的な使用に留め、基本的にはバランスの良い食事と十分な休息で疲れを取ることを意識しましょう。
4-3. 食事を抜く
食事を抜くことも、疲労回復には悪影響です。
食事を摂らないと、体に必要なエネルギーやビタミン類が不足し、筋肉の修復や免疫維持能力が低下します。
また、エネルギー不足が続けば集中力も落ち、余計に疲労感を強く感じるようになってしまうのも注意点です。
さらに、空腹が続くとストレスホルモンの「コルチゾール」が過剰に分泌されるため、疲れも増します。
忙しい場合は軽食をとるなどして、なるべく欠食は避けましょう。
体力回復の方法に関するよくある質問3選

体力回復の方法に関するよくある質問として、今回は以下をピックアップしました。
- 元気が出る食べ物はないの?
- 即効性の高い疲労回復の方法は?
- 病み上がりの体力回復方法として何がおすすめ?
多くの方が悩みやすい部分なので、ぜひ参考にしてみてください。
5-1. 元気が出る食べ物はないの?
元気が出る食べ物として、以下の食品をピックアップしました。
以下の食品をバランスよく食事メニューに取り入れることで、体力回復につながりやすくなるでしょう。
| カテゴリー | おすすめ食品 |
| 肉類 |
|
| 魚類 |
|
| 穀類 |
|
| 果物類 |
|
元気が出る食べ物について、詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
疲労回復に役立つ食べ物5選!疲労の原因も細かく解説 >>
5-2. 即効性の高い疲労回復の方法は?
即効性の高い疲労回復の方法として、主に以下が挙げられます。
| 即効性の高い 疲労回復の方法 |
体力回復に つながりやすい理由 |
| 入浴 |
|
| ストレッチ |
|
| マッサージ |
|
| 瞑想 |
|
いずれも短時間で取り組みやすいので、積極的に日常生活に取り入れるのがおすすめです。
特に入浴やストレッチ、マッサージや瞑想は、寝る前でも取り組みやすいので初心者の方もチャレンジしてみましょう。
5-3. 病み上がりの体力回復方法として何がおすすめ?
病気が治ったばかりで、まだ体力が元通りではない病み上がりの時の体力回復方法としては、以下が取り組みやすく、おすすめです。
| 病み上がりの 体力回復方法 |
病み上がりの体力回復 方法としておすすめな理由 |
| 消化に良い食べ物を補給する |
|
| 水分・電解質をこまめに補う |
|
| 軽いストレッチを行う |
|
病み上がりの状態は、特に体力が落ちているタイミングです。ハードな運動や仕事は避け、少しずつ回復することを意識しましょう。
体力を回復する手段として漢方由来のサプリメントがおすすめ!

自然治癒力を高める手段としては、漢方由来の成分を含むサプリメントの継続的な使用がおすすめです。
「身体に良いサプリメントなら何でもいいのでは?」と思うかもしれませんが、体の疲れには複数の原因があるため、単一成分のサプリメントを使用しても、疲労回復の根本的な改善は期待できません。
体を部位ごとではなく、全体でとらえる東洋医学の考え方に基づいた漢方(伝統生薬)は、全身の自然治癒力を高める働きがあります。
特定の症状だけでなく、心身のバランスを整えて体質改善を目指す効果もあるため、疲れにくい身体を手に入れられるようになるでしょう。
「体の疲れをしっかりと取りたい」「市販のサプリメントではなくしっかりとしたものを使いたい」と考えているのであれば、漢方由来の成分を含むサプリメントの利用も検討してみてください。
疲労回復サプリどれを選べばいいか?疲労の原因別おすすめサプリについて専門家が解説 >>
まとめ
体力が回復しない原因として、睡眠不足や栄養バランスの悪さなどさまざまな原因が挙げられます。
当てはまっている原因を見つけ、心当たりがあるものから対策していくと効率的です。
体力を回復させる方法の基本として、6~8時間の睡眠確保、栄養バランスを考えた食事、定期的なストレス発散などがあります。いずれも実践しやすいので、優先順位が高いものから取り組んでみましょう。
もし「忙しくて食事や運動の時間を確保できない…」という方は、漢方由来のサプリメントを摂取することがおすすめです。身体の自然治癒力を高め、疲れにくい身体を手に入れられるようになるでしょう。
【セルフチェック付き】疲れが取れない40代女性はどのサプリを選べばいいか。専門家が解説 >>