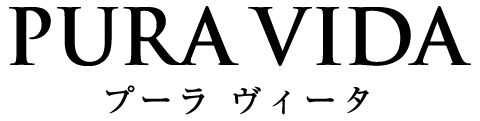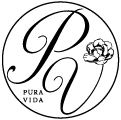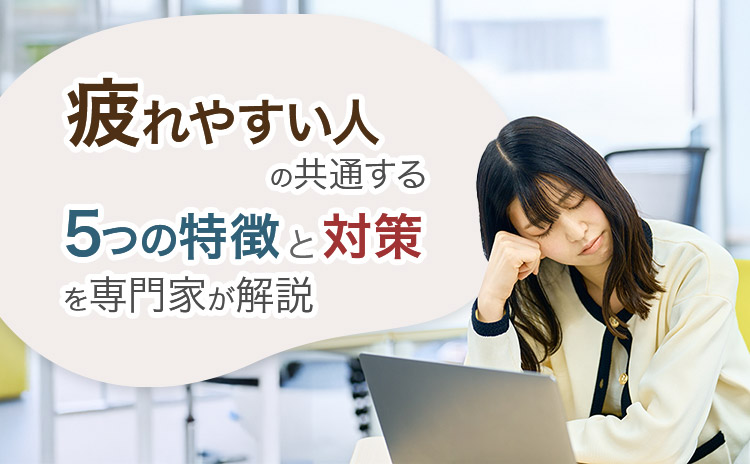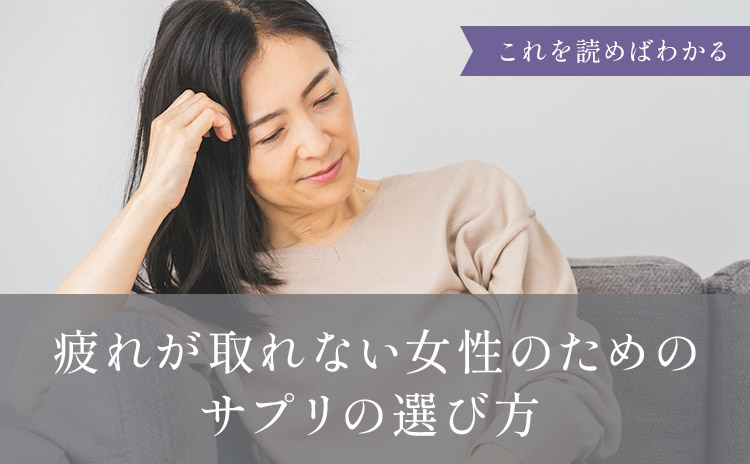「最近ほんとにすぐ疲れる…これって年齢のせい?」
「とにかくこのだるさをなんとかしたい!簡単にできることはないの?」
そんな風に感じている人は、もしかすると“疲れやすい人”に共通する特徴に当てはまっているかもしれません。
生活習慣や体質、考え方のクセなど、疲れやすさにはいくつかの共通点があります。
そこで本記事では、疲れやすい人について、以下の内容を解説します。
| この記事でわかること |
|
慢性的な疲れに悩んでいる方は、ぜひチェックしてみてください。
疲れやすい人の共通点は、睡眠不足、欠食、栄養の偏り、運動不足、ストレス蓄積の5つです。改善には、睡眠時間の確保、1日3食の規則正しい食事、適度な運動、こまめなストレス発散といった生活習慣の見直しが不可欠です。また、自然治癒力を高めるために、複数の症状にアプローチできる和漢サプリメントの活用も有効な手段の一つです。
目次
疲れやすい人に共通する5つの特徴

疲れやすい人に共通する5つの特徴として、以下をピックアップしました。
- 睡眠不足に陥っている
- 食事を抜いている
- 栄養バランスが悪い
- 運動する習慣がない
- 常にストレスが溜まっている
ご自身に当てはまっていないか、セルフチェックしてみましょう。
1-1. 睡眠不足に陥っている
睡眠不足は単なる眠気にとどまらず、心身に蓄積する「睡眠負債」として深刻な不調を引き起こします。
脳のパフォーマンスが低下し、集中力や判断力が鈍くなるほか、気分の落ち込みや意欲の低下といった精神面にも悪影響を与えます。
慢性的な睡眠不足は、うつ病に似た症状を引き起こすこともあるため注意が必要です。
疲れを感じやすい人は、睡眠の質や量に目を向け、生活リズムを整えることから見直しましょう。
睡眠障害について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてみてください。
知っているようで知らない「睡眠の質」の重要性。睡眠の質を上げる秘訣を専門家が解説 >>
1-2. 食事を抜いている
「朝は食べない」「昼は軽く済ませる」などの食習慣は、エネルギー不足を招き、疲れやすい体質をつくります。
脳の主なエネルギー源であるブドウ糖が不足すると、思考力や集中力が低下し、日中に強い倦怠感を感じやすくなります。
また、食事を抜くことで体内時計が乱れ、自律神経も不安定になるのが難点です。さらに血糖値の急上昇を招いて太りやすくなるなどの問題にも注意しなくてはなりません。
毎日規則正しく食事を摂ることが、疲労回復への第一歩となるでしょう。
1-3. 栄養バランスが悪い
見た目には食事量が十分でも、栄養素が偏り、タンパク質やビタミン、ミネラルといった特定の栄養素が不足すると、体は十分に機能しません。
特に、糖質や脂質に偏りがちな食生活では、エネルギーを効率的に使うために必要なビタミンB群が不足し、代謝が滞って疲労感が蓄積します。
さらに、甘いものを摂りすぎると血糖値の乱高下が起こり、結果的に強い眠気やだるさを引き起こすこともあり得るでしょう。
日々の疲れを感じやすい人は、タンパク質やビタミン、ミネラルを意識した食事を心がける必要があります。
| 参考: | 慢性疲労 -クスリになる食材あれこれ--特定非営利活動法人 日本成人病予防協会 |
1-4. 運動する習慣がない
「疲れているから運動できない」と感じる人ほど、実は運動不足が原因の可能性があります。
運動量が少ないと体力や筋力が低下し、日常のちょっとした動作でも疲れやすくなってしまいます。また、血流が滞ることで老廃物が溜まりやすく、慢性的な疲労感を引き起こす要因になりかねません。
厚生労働省では「週2回以上・1回30分以上の運動を1年以上継続する」ことを推奨しています。
まずは散歩や軽いストレッチから始めてみましょう。
1-5. 常にストレスが溜まっている
仕事や人間関係、将来への不安など、日常の中にはストレスの原因が数多く潜んでいます。これらが解消されずに蓄積すると、心身ともに疲弊し、慢性的な疲労感に陥ってしまうかもしれません。
感情のコントロールが難しくなり、イライラや落ち込み、不眠などの症状が現れることも。
精神的な疲れは、身体のパフォーマンスにも大きな影響を及ぼします。
定期的にリフレッシュの時間を設け、ストレスをこまめに発散することが、疲れにくい体づくりにつながるでしょう。
以下の記事も参考にしたうえで、対策してみてください。
イライラの症状と原因。関連する病気や対処法も解説 >>
疲れやすい人が今すぐ試すべき5つの対策

疲れやすい人が今すぐ試すべき5つの対策として、以下が挙げられます。
- 睡眠時間を確保する
- 食生活を見直す
- 栄養価の高い食べ物を摂取する
- 運動する習慣を作る
- 定期的にストレスを発散する
すぐに取り組めるものも多いので、ぜひ参考にしてみてください。
2-1. 睡眠時間を確保する
疲れやすさを感じているのであれば、まずは睡眠から見直してみましょう。
成人の場合、最低でも6時間以上の睡眠が推奨されており、毎日決まった時間に起床して朝日を浴びることで体内時計が整いやすくなります。
深い眠りを得るには、寝る前の過ごし方にも意識を向けることが大切です。
とくに、就寝前のスマートフォン操作は、ブルーライトによって睡眠の質を下げてしまうため注意が必要です。
入眠前にスマートフォンを触る癖がある場合、意識的に改善しましょう。
2-2. 食生活を見直す
健康的な体づくりには、バランスのとれた食生活が欠かせません。1日3食を規則正しく摂ることが基本で、とくに朝食は一日のエネルギー源として重要です。
また、よく噛んでゆっくり食べることで消化が助けられ、体への負担を軽減することにもつながります。
炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラルといった5大栄養素を意識して摂取することで、疲れにくい体を内側からサポートしましょう。
2-3. 栄養価の高い食べ物を摂取する
体の機能を支えるためには、栄養価の高い食材を選ぶことがポイントです。筋肉や臓器の維持に欠かせないたんぱく質は、肉や魚、卵、大豆製品などからバランス良く摂るのがおすすめです。
さらに、体調を整えるビタミンやミネラルは野菜や果物、乳製品から補うようにしましょう。
同じものばかりに偏るのではなく、さまざまな食材を組み合わせることが、疲労回復と健康維持につながります。
以下の記事も参考にして、毎日の食事を考えましょう。
疲労回復に役立つ食べ物5選!疲労の原因も細かく解説 >>
| 参考: | 栄養バランスに配慮した食生活には どんないいことがあるの?-農林水産省 |
2-4. 運動する習慣を作る
適度な運動は、体力の向上だけでなく、ストレスの軽減や睡眠の質の向上にもつながる重要な習慣です。運動が苦手な方も、まずは「毎日10分歩く」といった無理のない目標から始めましょう。
少しずつ習慣化することで、身体が活性化し、疲れにくい体質へと近づいていきます。
また、運動によって分泌されるホルモンが精神の安定にもつながるため、心身ともに健康を保つために取り入れていきたい習慣です。
運動習慣がない場合は、以下のような軽い運動から始めてみましょう。
| 運動 | 特徴 |
| ジョギング |
|
| ランニング |
|
| スイミング |
|
以下の記事も参考にして、体づくりを始めてみてください。
自宅で美しいからだに必要な筋肉をつける ボディメイクのスペシャリストが解説 >>
2-5. 定期的にストレスを発散する
疲れの原因には、身体的な要素だけでなく、精神的なストレスも大きく関係しています。ストレスが蓄積すると、自律神経が乱れて慢性的な疲労感を招くおそれがあります。
そのため、自分に合った方法でこまめにストレスを発散することが重要です。
趣味に没頭する、気の合う友人と話す、軽い運動や入浴、深呼吸などは副交感神経を優位にして心身をリラックスさせます。疲れをため込まない生活習慣を意識しましょう。
疲労回復のコツについては、以下の記事でも解説しています。
【医師監修】もう疲れない!今日からできる簡単疲労回復術 >>
疲れやすい症状をそのまま放置する3つのリスク
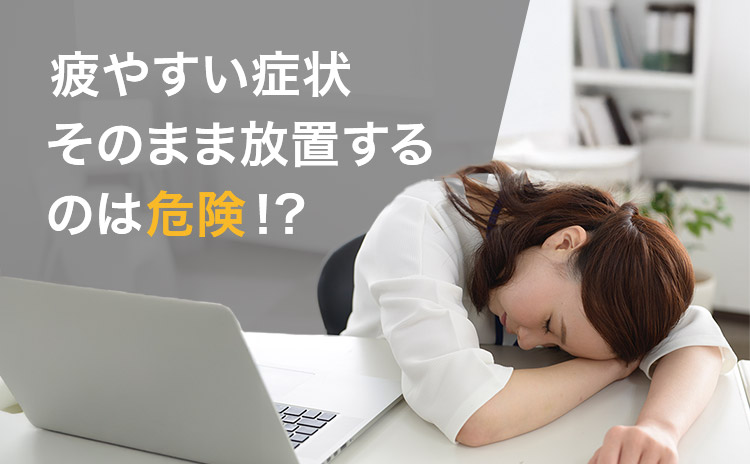
疲れやすい症状をそのまま放置する3つのリスクとして、以下が挙げられます。
- 生活の質が低下する
- 仕事の効率が下がる
- 心の不調につながる
現在、疲れやすさを感じているのであれば、必見の内容です。
3-1. 生活の質が低下する
疲労感が続くと、家事や趣味、運動など日常的な活動への意欲が薄れて「なんとなくやる気が出ない」と感じることが増えていきます。外出を避け、人付き合いも控えるようになることで、精神的な充実感も失われていくでしょう。
さらに、疲れに加えて頭痛や発熱、めまい、筋肉痛などの身体的な不調が表れることもあり、以前のように行動できなくなってしまいます。
これにより、気づかないうちに毎日の活力が失われ、無気力な生活に陥ってしまう可能性があるので早急に対策を行いましょう。
3-2. 仕事の効率が下がる
疲れを放置すると、集中力や思考力、注意力といった認知機能が著しく低下します。その結果、ミスが増えたり判断が遅れたりと、作業効率が大幅に落ちてしまいます。
これが積み重なると、職場での評価が下がり、人間関係にまで悪影響を及ぼすこともあるでしょう。
最悪の場合、疲労が限界を超え、休職や離職に追い込まれるケースもあるため、決して油断はできません。
3-3. 心の不調につながる
慢性的な疲労は、心と体のバランスを司る自律神経を乱し、メンタル面に悪影響を及ぼします。気分の落ち込み、不安感、イライラ、やる気の低下といった症状が現れ始めると、それは心のサインです。
さらに、脳内の神経伝達物質の働きにも支障が出ることで、うつ状態に近い症状が出ることもあります。「少し疲れているだけ」と放置せず、早めのケアや医療機関での相談が大切です。
疲れやすい人の特徴に関するよくある質問2選

疲れやすい人の特徴に関するよくある質問2選として、以下を集めました。
- スタミナがある人の特徴は?
- 体力は何歳から落ちますか?
多くの方が悩みやすい部分なので、チェックしてみましょう。
4-1. スタミナがある人の特徴は?
スタミナとは、体を長時間動かしても疲れにくい「全身持久力」のことです。
これは心肺機能が高く、酸素を効率よく取り入れてエネルギーに変換できる体の状態を意味します。スタミナがある人は、日常の活動や運動でも息切れしにくく、疲労の回復も早い傾向があります。
また、スタミナは身体的な能力だけでなく、困難に立ち向かう精神的な持久力も含まれる場合があります。
体力だけでなく気力にもゆとりがある人は、仕事や人間関係においても安定したパフォーマンスを発揮しやすいといえるでしょう。
| 参考: | なぜ全身持久力が必要なのか -健康と全身持久力の関連性-厚生労働省 |
4-2. 体力は何歳から落ちますか?
体力のピークは意外と早く、男性では17歳頃、女性では14歳頃に達するといわれています。
その後は20歳を過ぎると徐々に低下し始めますが、筋肉量などの体力のベースは40代ごろまで比較的安定して維持されることが一般的です。
ただし、運動不足や生活習慣の乱れが続くと、筋力や持久力は加速度的に低下してしまいます。
逆に、適度な運動を継続している人は、年齢に関係なく高い体力を維持することも可能です。
体力の衰えを感じ始めたら、年齢だけでなく生活習慣も振り返りましょう。
疲れやすいと悩んでいるのであればサプリメントが手段の1つとしておすすめ!

疲れやすい人が、疲れにくく、若々しい心身を保つには、病名のつかない不調、いわゆる未病に対する『自然治癒力』を高めるしかありません。そのためには、サプリメントを活用するのも一つの手段です。
ただし、疲れの原因が複数にわたっている場合は、一般的な「足りないものを補う」という役割だけのサプリメントでは、根本的な解消にならない可能性があります。
疲れやすい人は、疲労感だけでなく、身体のだるさ、筋肉痛、頭痛、月経不順、ほてり、不眠、冷えなど複合的な症状が現れることが多いからです。
このような観点から、おすすめしたいのが漢方由来の成分を含んだ和漢サプリメントです。
東洋医学から生まれた伝統生薬や和漢ハーブには、自然治癒力を高め、心身のバランスを整える効果があります。
疲れやすいといった症状が続く場合は、複数の原因や症状に対応できるように、漢方由来の成分を含んだ和漢サプリメントを選んで日常的に摂取してみましょう。
【セルフチェック付き】疲れが取れない40代女性はどのサプリを選べばいいか。専門家が解説 >>
まとめ
疲れやすい人に共通する原因として、「睡眠不足」「食事を抜く」「栄養バランスの偏り」「運動不足」「ストレスの蓄積」などが主に挙げられます。
対策としては「睡眠時間の確保」「食生活の見直し」「栄養価の高い食材の摂取」「運動の習慣化」「ストレス発散」などを行い、早急に対処することがおすすめです。
また、基本的な対策はもちろん、漢方由来の成分を含んだサプリメントをあわせて摂取することで、さらに高い効果を得られる可能性があります。
生活習慣の見直しだけではなく、サプリメントという解決策も視野に入れて疲れやすさの対策を行っていきましょう。
疲労回復サプリどれを選べばいいか?疲労の原因別おすすめサプリについて専門家が解説 >>