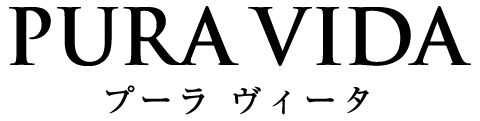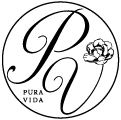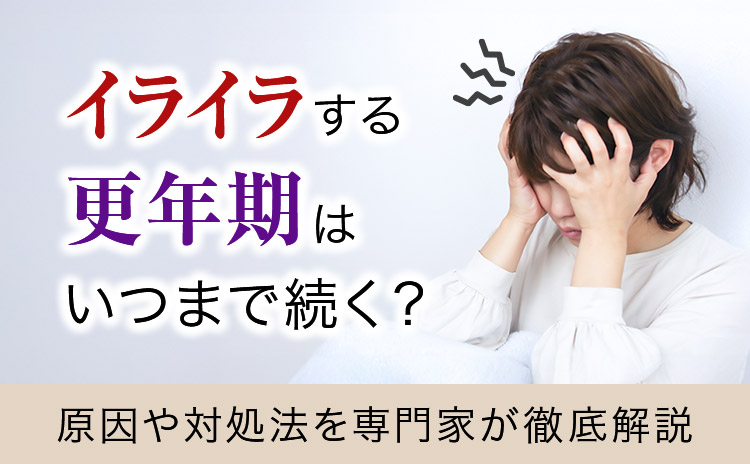「ちょっとしたことで旦那や子どもにきつく怒ってしまった……」
「思い通りにいかないとイライラする」
「このイライラって、更年期が原因?いつ終わるの?」
このような悩みや不安を抱えていないでしょうか?どうしようもなくイライラしてしまう原因は、もしかすると更年期によるホルモンバランスの乱れによるものかもしれません。
更年期には、女性ホルモンが減少することにより、イライラや不安をはじめとするさまざまな症状が現れます。
本記事では、更年期のイライラに関する以下の内容について詳しく解説します。
| この記事でわかること |
|
「イライラしたくないのにコントロールできない」「イライラがずっと続くのではないか」とお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
更年期とは
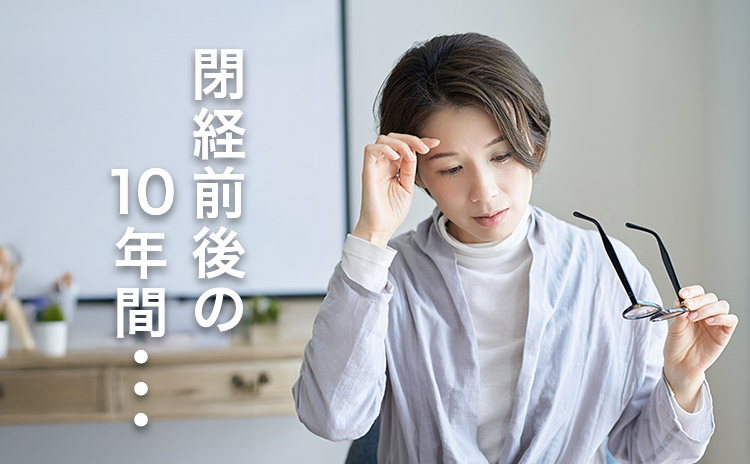
更年期とは一般的に、閉経前後の10年間(45~55歳ごろ)のことをいいます。
卵巣の機能が低下することで、女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌が減少し、次のようなさまざまな症状が現れます。
- イライラ
- 不安
- 気分の落ち込み
- 集中力の低下
- 疲労感 など
- ほてり
- 発汗
- 不眠
- だるさ
- 頭痛
- めまい など
| 参考: | 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト |
更年期で意味もなくイライラする原因
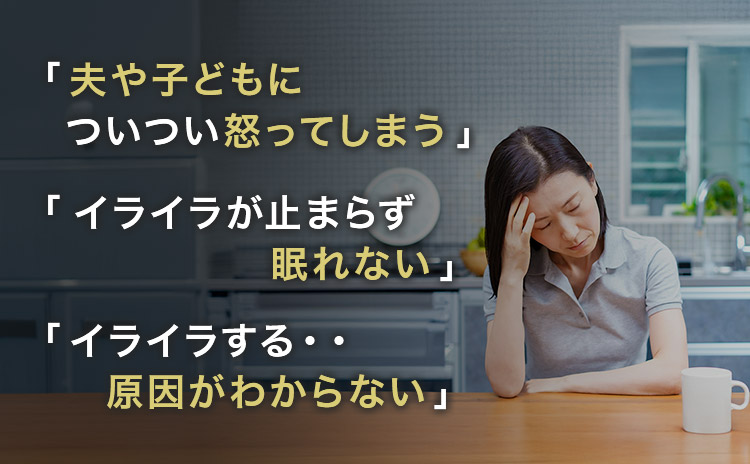
「夫や子どものちょっとした言動や行動が許せず、つい怒ってしまう」
「イライラが止まらず眠れない」
「イライラするけど原因がわからない」
このようなつらいイライラの症状は、なぜ起こるのでしょうか。
更年期でイライラしてしまう主な原因は、「エストロゲン」と呼ばれる女性ホルモンの減少です。
エストロゲンの低下は、自律神経や感情のコントロールに影響します。そのため、イライラや不安などの症状が現れやすいのです。
また、40~50代の女性は、責任の重いポジションでの仕事や、子どもの反抗期、親の介護など、ストレスを感じやすい環境にいる方が多いでしょう。これらの環境やストレスが、つらいイライラを引き起こす要因になっているのかもしれません。
エストロゲンの減少は、気分を安定させるホルモンである「セロトニン」の産生にも影響します。エストロゲンの低下によってセロトニンが不足すると、感情のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなってしまいます。
更年期症状はいつまで続くのか

更年期のイライラは永遠に続くわけではなく、一過性のものです。次第に身体がホルモンの低下に慣れてくるため、閉経後数年で症状が改善する場合がほとんどだとされています。
加えて、日々の生活習慣を見直したり、適切なケアを取り入れたりすることで、イライラを和らげることも可能です。
イライラして家族や身近な人に当たってしまい、コントロールできない歯がゆさや後悔を感じている方も多いでしょう。
つらいかもしれませんが、イライラしてしまうのはあなたが悪いのではなく、ホルモンバランスの影響によるものです。自分自身を責めすぎず、「今は体の変化の時期なんだ」と受け止め、少しずつできることから取り組んでいきましょう。
更年期障害のほかにイライラを引き起こす病気
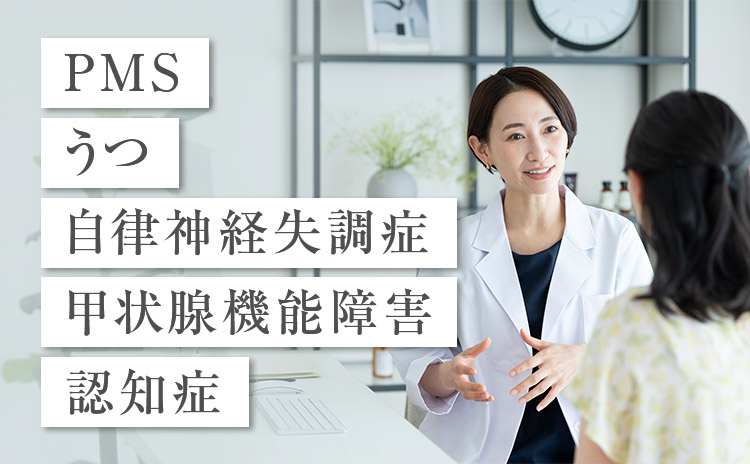
イライラを引き起こす原因には、更年期のホルモンバランスの乱れの他にも、次のようなものがあります。
- PMS
- うつ
- 自律神経失調症
- 甲状腺機能障害
- 認知症
それぞれの病気の特徴や症状について、詳しく見ていきましょう。
4-1. PMS
PMS(月経前症候群)とは、生理の3〜10日ほど前から現れる、精神的・身体的な症状のことです。具体的には、イライラや不安、胸の張り、頭痛、むくみなどが現れます。
多くの場合、PMS症状は月経がはじまると緩和します。イライラするタイミングが毎回生理前で、生理がはじまるとよくなる方は、PMSでイライラしているのかもしれません。
PMSについてより詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
【医師監修】PMSはいつから始まる?出現パターンや妊娠・病気との見分け方を婦人科医が解説 >>
4-2. うつ
うつ病は、脳内の神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリンの量が減ることで起こる病気です。
気分の落ち込みが代表的な症状ですが、イライラや怒りっぽさが目立つタイプのうつ病も存在します。
イライラや不安、食欲の低下などの症状が数週間以上続くようであれば、早めに精神科や心療内科へ相談しましょう。
4-3. 自律神経失調症
自律神経失調症とは、自律神経のバランスが乱れることで心身に不調が出る病気です。
自律神経は「交感神経」と「副交感神経」からなり、呼吸や心拍、体温の調節といった生命維持にかかわる働きを担っています。
自律神経失調症の主な原因はストレスや生活習慣の乱れ、ホルモンバランスの変化であり、自律神経が乱れると、イライラや動悸、息苦しさ、吐き気、不眠などのさまざまな症状が現れます。
4-4. 甲状腺機能障害
甲状腺ホルモンの分泌異常も、イライラする原因のひとつです。
甲状腺は喉仏のすぐ下にある器官であり、甲状腺ホルモンは全身の代謝を調整するホルモンです。とくに、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)では甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、体が常に興奮状態になります。
交感神経が活発になると、些細なことに過剰反応したり、イライラしやすくなったりします。そのほかにも、動悸や発汗、体重減少などの症状が見られるのが特徴です。
4-5. 認知症
認知症と聞くと「物忘れ」のイメージが強いかもしれませんが、「怒りっぽくなる」「些細なことでイライラする」など、認知機能の低下により感情のコントロールが難しくなることもあります。
日本では、65歳以上の約12%が認知症だとされています。また、認知症予備軍を含めると、65歳以上の3人に1人が、何らかの認知機能の低下を抱えていることになります。
イライラや物忘れなど、日常生活に支障が出る程度の症状が出ている場合は、早めに医療機関に相談しましょう。
イライラが止まらない!更年期症状を抑える7つの方法

更年期のイライラを抑える方法には、主に次のようなものがあります。
- 食生活の改善
- 適度な運動を取り入れる
- 睡眠の質を高める
- サプリメントを取り入れる
- ストレス源から離れる
- 家族に理解してもらう
- 医療機関に相談する
止まらないイライラで悩んでいる方は、日常生活に取り入れやすいものから試してみてください。
5-1. 食生活の改善
更年期のイライラには、栄養不足が関与している可能性があります。外食が多い方や、食事内容の偏りを感じる方は、三大栄養素である「糖質・たんぱく質・脂質」のバランスを意識してみてください。
納豆や豆腐などの大豆製品に含まれる「イソフラボン」は、女性ホルモンに似た働きを持ち、更年期症状の緩和に役立つとされています。
また、気分を安定させるホルモンである「セロトニン」をつくるためには、トリプトファンと呼ばれるアミノ酸が必要です。トリプトファンは、サーモンやマグロ、卵、バナナなどに多く含まれているので、意識的に取り入れてみてください。
なお、コーヒーやお酒に含まれるカフェインやアルコールは、自律神経を刺激してイライラを悪化させることもあるため、飲みすぎには注意しましょう。
5-2. 適度な運動を取り入れる
適度な運動はストレスを軽減し、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。なかでもウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの分泌を促し、気分の安定をサポートします。
天気がよい日は、日光を浴びながらの運動もおすすめです。日光を浴びることでもセロトニンの分泌が活発になり、気分のリフレッシュにつながります。
5-3. 睡眠の質を高める
睡眠不足が続くと、ホルモンや神経の働きに影響を与え、イライラしやすくなったり、気持ちが不安定になったりすることがあります。
ぐっすり眠るためには、寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトを避けることが大切です。ブルーライトは脳を刺激し、眠りをさまたげる原因になります。
就寝前には、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かりましょう。深部体温を一旦上げてから自然に下がるタイミングで眠りにつくことで、睡眠の質を上げる効果が期待できます。
5-4. サプリメントを取り入れる
栄養はできるだけ食事からとるのが基本ですが、不足しやすい成分はサプリメントで補うのもひとつの方法です。
「大豆イソフラボン」や「エクオール」、「プラセンタ」などは、女性ホルモンのバランスが乱れやすい更年期におすすめの成分として注目されています。
また、女性ホルモンの合成を助ける「ビタミンB6」は、イライラや不安、気分の落ち込みなどの緩和に役立つ可能性があると研究で示されています。
下記の記事では、更年期とエクオールのサプリメントに関して詳しく解説しているので、興味のある方は参考にしてみてください。
| 参考: | 中高年女性のうつ症状はビタミンB6摂取量の低下と関連している|アメリカ国立衛生研究所 |
更年期をサポートするエクオールサプリの効果と副作用について専門家が徹底解説 >>
5-5. ストレス源から離れる
ストレスがたまり続けると、交感神経が優位な状態が続き、イライラや不眠といった不調の原因になります。仕事や育児、家事、介護など、ストレスのもとは人それぞれですが、可能であれば少し距離を置いてみることも大切です。
たとえば、仕事がつらいと感じるなら転職を考えてみたり、育児や家事が負担になっているなら家族や周囲の人に助けを求めてみたり、少しでもストレスから離れる時間をつくることで、心に余裕が生まれるかもしれません。
また、ヨガやアロマテラピーなど、リラックスできる趣味を見つけるのもおすすめです。家でも職場でもない、ほっとできる「第三の居場所(サードプレイス)」を持つことも、ストレスの軽減につながるでしょう。
5-6. 家族に理解してもらう
更年期の症状は外からは見えにくいため、周囲の理解を得るのが難しいこともあります。それでも一人で我慢せず、家族に自分の気持ちを伝えることはとても大切です。
「こういうときにこうしてほしい」といった具体的な要望をリスト化して伝えると、相手も行動しやすくなるでしょう。直接伝えるのが難しい場合は、子どもや共通の友人など、第三者を通じて気持ちを伝えるのもひとつの方法です。
イライラしてつらい気持ちを家族が理解し、寄り添ってくれるだけで心が軽くなることもあります。無理に抱え込まず、少しずつでも共有していきましょう。
5-7. 医療機関に相談する
更年期のイライラが長期間続き、日常生活に支障が出るようであれば、医療機関へ相談する方法もあります。
婦人科では、薬剤で女性ホルモンを補う「ホルモン補充療法(HRT)」や、体質に合わせた漢方薬など、症状に応じた治療を受けられることがあります。
また、心の不調が強い場合には、カウンセリングや心理療法といった心のケアも効果的です。
イライラには複合成分を配合したサプリメントがおすすめ
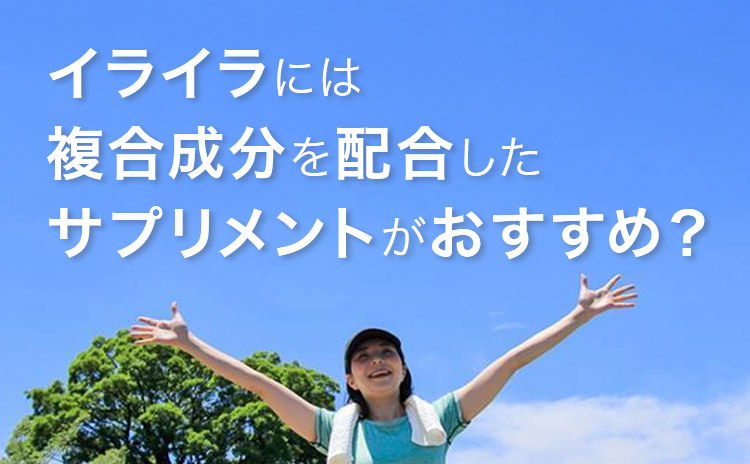
更年期のイライラや不安といった不調には、1つの成分だけではなく、複合成分を配合したサプリメントの活用がおすすめです。
更年期の不調は、生理不順、冷え、めまい、多汗、疲労感、不安感…と、多岐に渡り複雑化しています。この複雑化した悩みにアプローチするためには、様々な成分を組み合わせたサプリメントを摂取することが重要です。
なかでも、東洋医学の考え(不調を引き起こす原因にアプローチして、健康バランスを整えていくこと)をベースにした、伝統生薬やスーパーフード由来のサプリメントは、体の内側から自然治癒力を引き出し、根本的な体質改善をサポートしてくれる点が魅力です。
東洋医学では、身体の不調や症状を「身体全体のバランスの崩れ」と捉えます。
その根幹にあるのが、万物を構成する要素を「木」「火」「土」「金」「水」の5つに分類し、それぞれの要素が支え合い、影響しあって、絶妙なバランスで成り立っているとする「五行論」です。
これは人間の身体にも同じことがいえ、東洋医学ではこの五行に人間の身体を支える5つの要素を当てはめています。
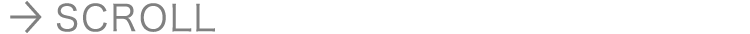
| 木 (肝) |
自律神経や情緒 | <女性特有の不調> 更年期の症状・生理不順・血の巡り |
| 火 (心) |
血液循環と精神・意識 | <心の安定> 不眠・ストレス・不安 |
| 土 (脾) |
消化吸収 | <体の巡り> 冷え・むくみ・消化不良 |
| 金 (肺) |
呼吸と体の潤い | <免疫力> 免疫力低下・アレルギー・呼吸器不調 |
| 水 (腎) |
成長や発育・生殖 | <身体機能> 肉体疲労・機能低下・肌老化 |
更年期による不調は「木(肝)」に当てはまるものなので、ここにアプローチできるサプリメントを、毎日の生活習慣の見直しとあわせて取り入れることで、心と体のバランスを整える手助けになるでしょう。
40代女性に必要なサプリを症状別に解説。更年期指数セルフチェック付き >>
まとめ
更年期によるホルモンバランスの乱れは、イライラや不安感、不眠など、心身にさまざまな影響を与えます。ときには家族との関係がぎくしゃくし、自分を責めてしまう方もいるかもしれません。
つらいイライラを和らげるためには、更年期の症状が現れる仕組みを知り、食事や運動、睡眠などの生活習慣を見直すことが大切です。
また、ストレスから少し距離を取ることや、自分に合ったリラックス法を見つけることも、気持ちを落ち着ける助けになります。
必要に応じて栄養を補うサプリメントを取り入れたり、症状がつらい場合には医療機関に相談したりする方法もあります。
更年期のイライラは、一生続くものではありません。自分自身を責めず、できる対処法から少しずつ取り組んでみましょう。