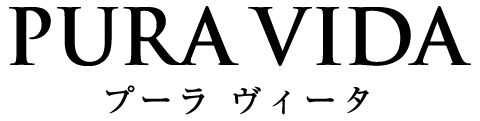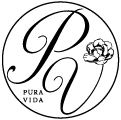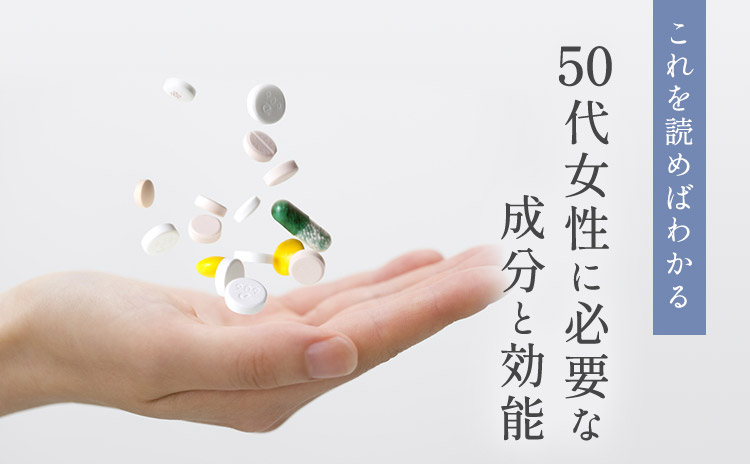「腸活って何から始めればいいの?」
「毎日続けられる簡単なやり方が知りたい…」
「食事や生活習慣を見直したいけど、どうすればいいの?」
このように悩んでいませんか?
腸活を行うと免疫機能が改善され、身体全体に好影響を与えます。
ところが方法がわからず、何から手をつければいいのかわからないという方も多いのが現状です。
そこで今回の記事では、以下の内容について解説します。
| この記事でわかること |
|
これから腸活を始めたいのであれば、必見の内容です。
この記事を読みながら、腸活を始めてみましょう。
正しい腸活のやり方5ステップ
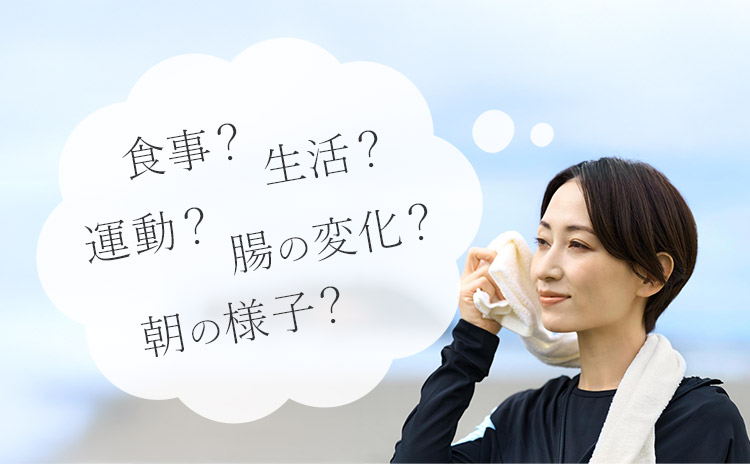
正しい腸活のやり方5ステップとして、以下の流れを意識しましょう。
- 腸に優しい食事を意識する
- 規則正しい生活リズムを作る
- 運動習慣を作る
- 自分の腸の変化をチェックする
- 朝の様子をもとに調整する
取り組みやすい流れになっているので、ぜひ参考にしてみてください。
1-1. 腸に優しい食事を意識する
腸の健康を考えるうえで、まず重要なのは食事の内容です。発酵食品や食物繊維が豊富な食品を積極的に選ぶことで、腸内の善玉菌を増やしやすくなります。
ヨーグルトや納豆、キムチ、味噌などの発酵食品は、腸内環境を整えるためにとくにおすすめです。
一方で、脂肪分の多い揚げ物や加工食品を過度に摂取すると、腸が消化に負担を感じて動きが鈍くなります。
頑張って善玉菌を増やそうとしていても、揚げ物やジャンクフードが多い食生活では効果が下がりかねません。
また、食事の時間を一定にすることで、腸がリズムよく動きます。朝・昼・夜の食事時間を概ね決めておき、それぞれで無理なく発酵食品や野菜などを取り入れてみましょう。
1-2. 規則正しい生活リズムを作る
意外と見落とされがちですが、毎日同じ時間に起きて寝るという生活リズムは、腸内の活動を安定させるうえでとても重要です。
腸は自律神経の影響を大きく受けるため、寝不足や夜更かしが続くと、不調を起こしやすくなります。
また、朝食をきちんと摂って腸を目覚めさせることは、自然なお通じや栄養吸収につながる大切な習慣です。
さらに、日中に適度な日光を浴びると体内時計が整い、夜もスムーズに眠りにつきやすくなります。
「腸活をしているのに効果が今ひとつ…」という方は、まず生活リズムが乱れていないかを見直してみましょう。
1-3. 運動習慣を作る
腸活では食事だけでなく、適度な運動による腸への刺激も必要です。
ウォーキングやヨガなどの軽い運動は、腸のぜん動運動(ぜんどううんどう:腸が波のように収縮すること)を促進するため、お通じがスムーズになりやすいとされています。
最近の研究では、運動量の増加は腸内の善玉菌の種類と数、微生物の多様性を増やす可能性があるということもわかっています。
| 参考文献: | 運動は腸内細菌叢を変化させ、健康に良い影響を与える |
無理なく運動を続けるには、1日30分のジョギングや散歩から始めてみるといいでしょう。
習慣として身につけば、腸内環境の改善だけでなく心身のリフレッシュ効果も期待できます。
1-4. 自分の腸の変化をチェックする
腸内環境の変化は目に見えにくいのが難点ですが、便の状態や排便のリズムは貴重なサインです。
便が硬くて出にくい、あるいは下痢をしやすいなどの状態が続いている場合、食事や睡眠、ストレスなどに原因が潜んでいるかもしれません。
お腹の張りや違和感が続く場合、摂取している食材が合っていない可能性も考えられるので、腸の変化はしっかりチェックしておきましょう。
スマートフォンにメモを残すだけでも、自分の腸の傾向を客観的に把握しやすくなります。
ストレスを強く感じた日は下腹部に重さを覚えやすいか、夜更かしをした翌日のお通じに変化はあるかなどを振り返り、必要に応じて食生活や生活リズムを調整してみましょう。
1-5. 朝の様子をもとに調整する
朝は、腸の動きが活発になりやすい時間帯です。もし朝の排便がスムーズでないと感じたら、飲む水分量を増やす、食物繊維の摂り方を工夫するなど、こまめに対策を考えてみましょう。
腸の働きが鈍いときは、適度な運動や十分な睡眠が取れているかも再確認しておくべきです。
とくに快便につながらない場合は、不溶性と水溶性の食物繊維をバランスよく取り入れると同時に、汗をかいた分の水分補給を意識してください。
腸内環境を整える方法については「腸内環境を整える5つの方法!セルフチェック方法なども解説」の記事もチェックしてみましょう。
腸内環境を整える5つの方法!セルフチェック方法なども解説 >>
腸活におすすめの3つのお手軽食事メニュー
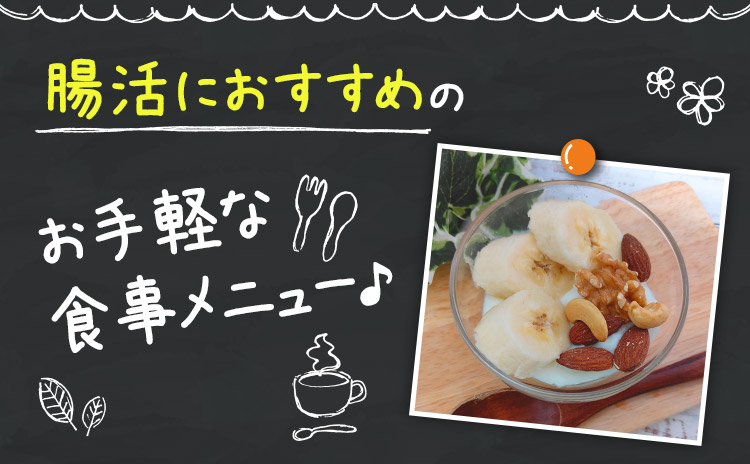
腸活におすすめのお手軽な食事メニューとして、以下の3つをご紹介します。
- ヨーグルトとバナナのオートミールボウル
- 納豆とアボカドの玄米丼
- 蒸し野菜と味噌スープのセット
それぞれの食事メニューのメリットについて、見ていきましょう。
2-1. ヨーグルトとバナナのオートミールボウル
ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、腸内の善玉菌を増やす大事な存在です。加えて、バナナの食物繊維が腸の動きをさらにサポートします。
また、オートミールは水溶性食物繊維を豊富に含むため、腸内での発酵を促し、善玉菌の活動を活性化しやすくおすすめです。
朝食にもぴったりで、腹持ちが良いのもメリットといえます。気軽に食べやすいメニューなので、積極的に朝食のメニューにとり入れてみましょう。
- バナナ1本を食べやすい大きさにカットする
- ヨーグルト(無糖)200gと、オートミール60gを混ぜ合わせる
- カットしたバナナをトッピングして完成
2-2. 納豆とアボカドの玄米丼
納豆菌は腸内フローラを整える効果が注目されており、納豆特有の粘り成分に含まれる酵素が栄養の消化吸収を高めてくれると考えられています。
※腸内フローラ:腸内に住んでいる細菌の集合体を表す言葉
アボカドはオレイン酸が豊富で、腸の滑りを良くしてくれるといわれています。
そして、玄米に含まれる食物繊維が腸内をきれいに保ち、満腹感の持続にも役立つため、過食を防ぐ効果も期待できるでしょう。
また、味つけを変えて、その日の気分でアレンジできるのもうれしいポイントです。
- 玄米ご飯150gを用意する
- アボカド1/2個の種と皮を取り、ひと口大にカットする
- 玄米ご飯の上にアボカドと納豆をのせる
- お好みで醤油やポン酢などを加えて和える
2-3. 蒸し野菜と味噌スープのセット
蒸し野菜と味噌スープのセットは、忙しいときでも手早く作れる便利な組み合わせです。
味噌には乳酸菌に近い発酵菌が含まれており、腸内での善玉菌の働きをサポートします。
蒸し野菜は油を使わず低カロリーで、野菜本来の甘みや栄養素をしっかり摂れるのも魅力です。
野菜に含まれる不溶性食物繊維は、腸のぜん動運動を刺激して排便を促しやすくしてくれるでしょう。
- ブロッコリー、人参、かぼちゃなどの食物繊維が豊富な野菜を用意する
- 食べやすい大きさにカットし、蒸し器や鍋を利用して蒸す
(鍋の場合は水を入れ、クッキングシートを敷いたザルに野菜を入れて、弱火で20~30分加熱すれば完成) - 玉ねぎやごぼうなどの野菜を薄く切る
- 水を入れた鍋に出汁パックを入れて火にかける
- 沸騰したら玉ねぎやごぼうなどの野菜を入れて、柔らかくなったら味噌を入れてひと煮立ちさせる
腸活を続ける3つのコツ

腸活を続ける3つのコツとして、以下が大切です。
- 少しずつやることを増やす
- いろいろな種類の食材を食べる
- 適度な運動を取り入れる
長続きするか不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。
3-1. 少しずつやることを増やす
腸活を成功させるには、最初から大きな目標を掲げるよりも、少しずつ新しい取り組みを積み重ねていく方がおすすめです。最初から完璧を目指すと続けることが難しくなり、挫折してしまうこともあります。
たとえば、朝食にヨーグルトを加える、夕食に納豆を取り入れるなど、簡単な工夫であれば無理なく続けやすいでしょう。
失敗しないためにもまずはごく小さな習慣から始めて、自分の腸の状態やペースに合わせながら、徐々にやることを増やしてみてください。
運動に関しても、いきなりハードなトレーニングを取り入れるのではなく、ジョギングやストレッチなど身体にやさしいメニューからスタートするのがおすすめです。
3-2. いろいろな種類の食材を食べる
腸内環境を改善するうえで大切なのは、いろいろな食材をバランスよく食べるということです。
発酵食品や食物繊維のみを頼りにするのではなく、ビタミンやミネラルなど他の栄養素にも目を向けると、腸内をはじめ身体全体を元気に保ちやすくなります。
野菜や果物、肉や魚などを幅広く取り入れることで、栄養素の偏りも減らせるようになるでしょう。
3-3. 適度な運動を取り入れる
腸の働きを高めるには、適度な運動も欠かせません。ウォーキングや軽めの筋トレなど体への負担が少ない運動は、血行を促進して腸への刺激にもつながりやすくなります。
とくに腹筋まわりをほぐしたり鍛えたりする運動は、腸のぜん動運動をサポートし、便秘予防におすすめです。
ただし、激しすぎる運動はストレスホルモンの増加によって、かえって腸に負担をかけることがあるため、身体が心地よいと感じられる範囲で行う必要があります。
こうした運動・食事・生活習慣を少しずつ改善していけば、腸活が習慣化し、より快適な日々を過ごしやすくなるでしょう。
初心者でも取り組みやすい運動を以下にまとめたので、参考にしつつ取り組むのがおすすめです。
| 運動 | メリット |
| ウォーキング |
|
| ストレッチ |
|
| スクワット |
|
| プランク |
|
腸活を続けるためのコツとして「腸内環境を改善する5つの方法!おすすめの食べ物も解説」の記事も参考になるので、ぜひチェックしてみてください。
腸内環境を改善する5つの方法!おすすめの食べ物も解説 >>
間違った腸活のやり方

間違った腸活のやり方として、以下に注意しましょう。
- 発酵食品のみ食べている
- 食物繊維を摂りすぎている
- オリゴ糖を過剰に摂取している
健康状態を損なうことにつながりかねないので、事前に確認してみてください。
4-1. 発酵食品のみ食べている
発酵食品は確かに腸内環境を整えるうえで欠かせない存在ですが、ヨーグルトや納豆など、特定のものばかりを食べ続けるのは控えましょう。
発酵食品だけでは摂取できる栄養素に限りがあるため、結果的に栄養バランスが偏ってしまう恐れがあります。
腸に良い食品を取り入れる一方で、野菜や果物、たんぱく質など幅広い栄養の摂取を意識しましょう。
加えて、食物繊維やオリゴ糖なども上手に組み合わせることで、食生活の土台をバランス良く保てるようになります。
| 食物繊維を多く含む食べ物 | オリゴ糖を多く含む食べ物 |
|
|
4-2. 食物繊維を摂りすぎている
食物繊維は腸内環境を改善するうえで重要ですが、過剰摂取はかえって便秘や下痢を引き起こすリスクを高めることがあります。
とくに、今まであまり食物繊維を摂っていなかった方が急に大量に取り入れると、腸内にガスがたまりやすくなり、お腹の張りや不快感を招きやすいので注意が必要です。
大切なのは少しずつ量を増やしていきながら、水溶性と不溶性の食物繊維をバランス良く摂ることです。
食物繊維の種類ごとの違いは以下の表にまとめているので、違いを理解しておきましょう。
| 食物繊維 | 特徴 |
| 水溶性食物繊維 |
|
| 不溶性食物繊維 |
|
便秘については「便秘によって肌荒れが起こる理由3選と5つの改善方法!サプリメントの選び方も解説」の記事で詳しくまとめているので、あわせてチェックしてみてください。
便秘によって肌荒れが起こる理由3選と5つの改善方法!サプリメントの選び方も解説 >>
4-3. オリゴ糖を過剰に摂取している
オリゴ糖は腸内フローラの改善機能を持っていますが、摂りすぎには注意が必要です。摂りすぎると、お腹の張りや下痢を引き起こすリスクがあり、健康状態を損ないかねません。
また、甘さに物足りなさを感じて大量に使用してしまい、カロリー過多になる恐れもあるので、摂りすぎは厳禁です。糖尿病のリスクなども高まりやすくなるので、摂取する際は量も意識しましょう。
腸活を続ける際の3つの注意点
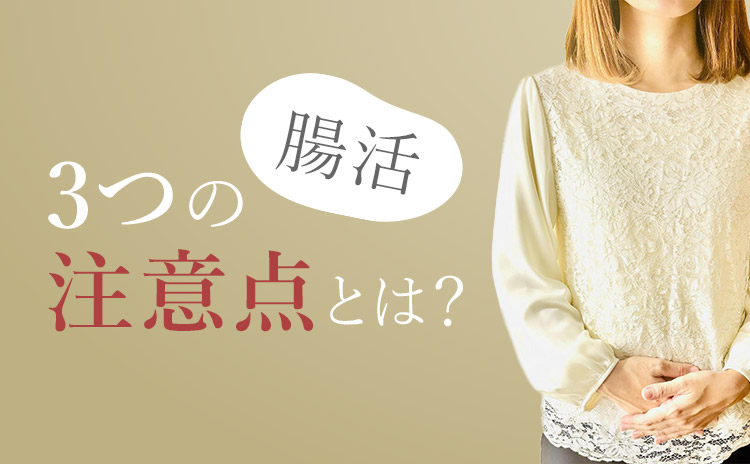
腸活を続ける際の3つの注意点として、以下を押さえておきましょう。
- 体質に合わない食品や飲料は控える
- 水分をしっかり摂る
- 生活習慣も見直す
なかなか腸活を続けられる自信がないという場合は、ぜひ参考のうえで取り組んでみてください。
5-1. 体質に合わない食品や飲料は控える
腸に良いとされる食品であっても、体質によっては逆効果になる可能性があります。たとえば乳製品や発酵食品が合わず、お腹を下してしまう方は少なくありません。
そのような場合は無理をして続けるのではなく、一度摂取を中止することも検討すべきです。
また、お腹が張りやすい人は、食物繊維を多く含む食品の摂取量に気をつけることが大切です。
自分の身体がどの食材を好み、どの食材で不快感が出やすいかを把握しておくと、腸のトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
5-2. 水分をしっかり摂る
便秘の原因にはさまざまな要素がありますが、水分不足も大きく関係します。
食物繊維を十分に摂取していても、水分が足りていないと便が固くなって排出しづらくなるため、腸活の効果が下がりかねません。
だからといって、冷たい飲み物ばかりを選ぶと腸の動きが鈍くなることがあるため、常温や温かい飲み物を意識的に取り入れるとよいでしょう。
加えて、市販のジュースには砂糖や果糖ブドウ糖液糖が多く含まれている場合が多く、悪玉菌のエサになりやすい点も見逃せません。
甘い飲み物を続けて摂ると、腸活を妨げる原因になるので注意してください。
また、糖分の代わりとして人工甘味料を選ぶ方もいるかもしれませんが、人工甘味料には腸の活動を悪化させるリスクがあることも最近の研究結果で分かっています。
腸の活動を改善させたいのであれば、甘いものや人工甘味料はなるべく控えましょう。
| 参考文献: | 腸菌細菌が人工甘味料の過剰摂取によって引き起こされる下痢を防ぐことを発見 |
5-3. 生活習慣も見直す
腸活は食事だけで完結するものではなく、運動や睡眠、そしてストレス管理などの生活習慣全体が大きく影響します。
慢性的な睡眠不足や強いストレスにさらされていると、自律神経が乱れて腸の働きが落ち込みやすくなります。
そこで、日々のスケジュールの中にリラックスできる時間を設け、適度に身体を動かす工夫を取り入れてみてください。ウォーキングや簡単なストレッチだけでも、血行を促進して、腸のぜん動運動をサポートしてくれます。
食事だけでなく、こうしたトータルな生活習慣の改善を図ることで、最終的に腸のコンディションを整えやすくなるでしょう。
腸活には発酵酵素を取り入れるのがおすすめ

発酵食品には、乳酸菌をはじめとして、腐敗物質の増加を抑制する善玉菌が豊富に含まれています。
善玉菌には、外から入ってくる病原体の侵入を防ぐ免疫細胞を活性化させる働きもあるため、 発酵食品を積極的にとることは、腸内環境を整えながら免疫力を高め、病気を予防するうえで効果的です。
とくに「発酵酵素」には、乳酸菌をはじめとした善玉菌が豊富に含まれており、摂取することでより腸活において高い効果を発揮します。
なお、東洋医学では、不調を改善して健康的な体を作っていくには「不調を引き起こす原因にアプローチして、心身のバランスを整えていくこと」が重視されます。
便秘や下痢など、身体の不調の改善を考えているのであれば、東洋医学の考えに基づいて作られた発酵酵素を積極的に摂取するのもおすすめです。
まとめ
腸活を正しく進めるためは、腸に優しい食事、規則正しい生活リズム、運動習慣などの行動が必要です。
行動を続けていくだけではなく、自分の腸の変化をチェック、朝の様子をもとに細かく調整するという改善も行うと良いでしょう。
また、腸活を挫折せずに続けていくためには、少しずつやることを増やす、いろいろな種類の食材を食べるなどの行動を意識することで続けやすくなります。
ただし、腸活を行う際、間違った方法もあるので注意が必要です。
たとえば、善玉菌、食物繊維、オリゴ糖など腸に良い栄養を過剰にとるのは逆効果を招きかねません。過剰摂取するのではなく、ほかの栄養素も取り入れながら食生活を見直し、正しい腸活を継続しましょう。
今回の記事では、取り組みやすい腸活のやり方をいくつかご紹介しました。
発酵酵素をより手軽に摂取するためにはサプリを活用するのがおすすめです。普段忙しく、なかなか時間が取れない場合などはとくに役立つでしょう。
食生活や生活習慣の見直しよりも手軽に取り組める方法なので、ぜひ検討してみてください。