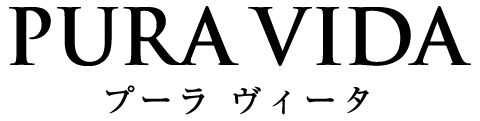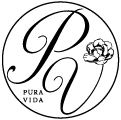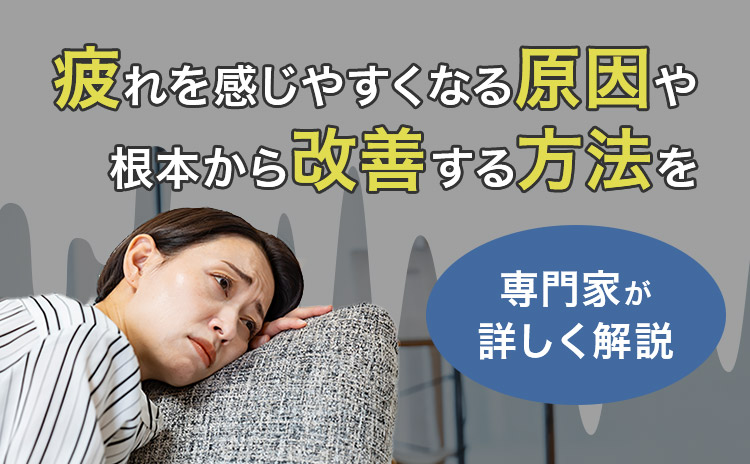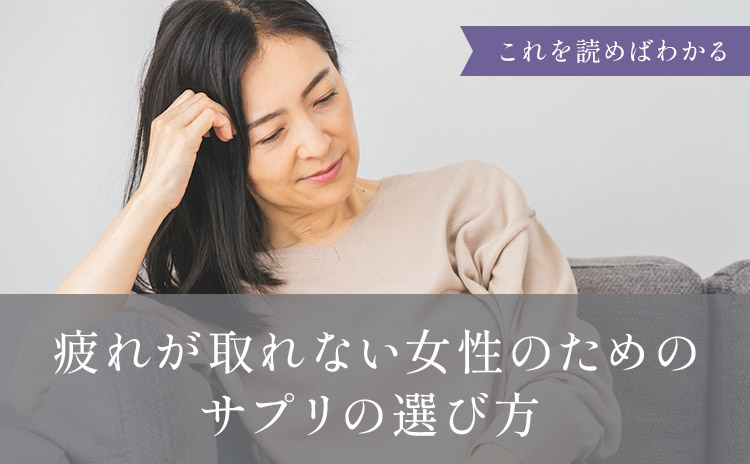「最近なんだかずっと疲れている気がする……」
「疲れやすい体質を改善する方法はないの?」
そんなお悩みを抱えていないでしょうか。仕事や家事など、やることはたくさんあるのに疲れて何もできない状態が続くと、自分を責めてしまう方も多いでしょう。
40代に入ると、ホルモンバランスや自律神経の乱れ、筋力量の低下といった体の変化により、慢性的な疲れを感じやすくなります。
この記事では、40代の女性が疲れを感じやすくなる原因や、疲れやすい体質を根本から改善する方法などについて詳しく解説します。疲れやすい体質でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
なんでこんなに疲れるの?40代の疲れの原因
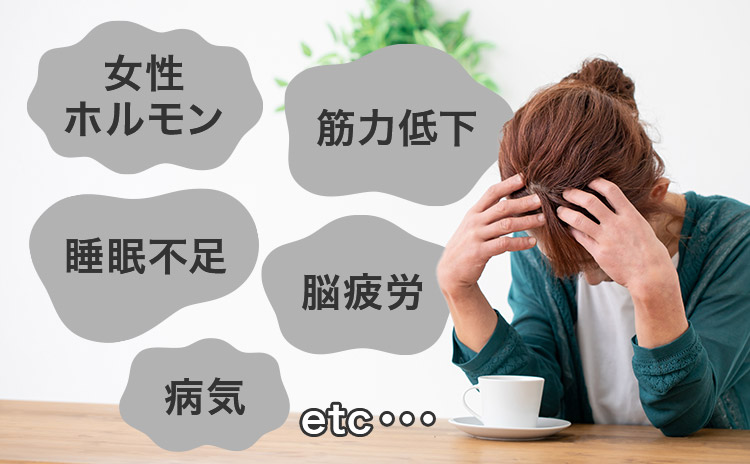
40代に入ってから、「以前は少し休めば回復していたはずの疲れが取れない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
ここでは、40代の女性が疲れを感じやすくなる原因について解説します。
1-1. 女性ホルモンの減少
女性は更年期(45~55歳頃)になると、女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌量が急激に低下します。
エストロゲンは、自律神経のバランスや血流のコントロールなどにも関係しているため、減少することで血行不良や代謝機能の低下などが起こりやすくなります。
その結果、だるさや疲れが取れないといった状態に陥りやすくなるのです。更年期の疲労は、一晩休めば元に戻るような一時的な疲労とは異なり、慢性的に続くことが特徴です。
| 参考: | 厚生労働省 働く女性のこころと体の応援サイト |
1-2. 筋力の低下
筋肉量は加齢とともに自然に減少し、とくに40代を過ぎたあたりからその傾向が顕著になります。
| 参考: | 健康長寿ネット サルコペニアとは | 健康長寿ネット |
筋肉は、体を動かすエンジンのような役割をもっています。
筋力が落ちると、同じ動作をするのにも、より多くのエネルギーを使うようになるため、少しの動作でも疲れやすくなったり、回復に時間がかかったりするのです。
1-3. 睡眠不足や脳疲労
40代は、仕事で責任のある立場に就きやすく、家庭では家事や育児に追われやすい時期です。
日々の忙しさで、睡眠時間を十分に取れていない方も多いのではないでしょうか。
十分な睡眠時間を確保しているつもりでも、浅い眠りが続くと回復力が追いつかず、朝起きたときに疲れを感じることも多いでしょう。
常に頭を使い続けていたり、ストレスを抱えたまま眠りについたりすると、脳が十分に休めず、「脳疲労」も蓄積されてしまいます。
1-4. 病気の影響
何をしても疲れが改善されず、だるさが長期間続くようであれば、次のような病気が原因となっている可能性もあります。
<慢性的な疲れを引き起こす可能性のある疾患>
- 更年期障害
- 鉄欠乏性貧血
- 自律神経失調症
- 甲状腺機能低下症
日常生活に支障が出るくらいの疲労感が長く続いたり、いつもと異なる症状が見られたりする場合は、内科や婦人科、心療内科などで一度相談してみることをおすすめします。
【セルフチェック付き】疲れが取れない40代女性はどのサプリを選べばいいか。専門家が解説 >>
東洋医学における疲れやすさの原因とは

東洋医学では、健康でいるためには「気・血・水」のバランスが整っていることが大切だと考えられています。
- 気(き):身体のエネルギー
- 血(けつ):血液や栄養分
- 水(すい):体液やうるおい
とくに加齢とともに起こりやすいのが、身体のエネルギーである「気」の不足や、栄養分である「血」の不足による疲れです。
また、胃腸(脾)の働きが低下することでも、栄養がうまく吸収されずにエネルギー不足となり、疲れやすさにつながることがあります。
疲れやすい人がやりがちなNG行動

「しっかり寝たはずなのに疲れが抜けない」
「なんとなく毎日だるい」
そのような慢性的な疲れを感じる原因は、日々の生活習慣に潜んでいるかもしれません。ここでは、疲れにつながりやすいNG行動とその理由を解説します。
3-1. 寝すぎ・寝だめで生活リズムが崩れる
平日の寝不足を解消するために、週末に長時間「寝だめ」していないでしょうか?
その「寝だめ」が、かえって疲れやすい体をつくる原因になっているかもしれません。休日に長時間眠ると体内時計が乱れ、平日の夜の寝つきが悪くなったり、朝にスッキリ起きられなくなったりすることがあります。
疲れをしっかり取るには、「長時間寝ること」よりも、「毎日同じ時間に寝て起きること」や「寝る前の過ごし方」が大切です。睡眠の質を高めるためにも、寝る前はスマホの使用やカフェインの摂取を避け、リラックスできる環境を整えましょう。
3-2. 外出する機会が少ない
日常的に外出の機会があまりなく、太陽の光を浴びる時間が不足すると、疲れやすさの原因になることがあります。
とくに、在宅ワークや家事中心の生活で屋内に居る時間が長い方は注意が必要です。
太陽光を浴びることで分泌される「セロトニン」は、気分を安定させたり、自律神経のバランスを整えたりする働きをもつ重要なホルモンです。
セロトニンが不足すると、慢性的な疲労感や無気力感、やる気の低下といった不調につながる可能性があります。
普段から屋内に居ることが多い方は、朝の散歩やベランダでの日光浴など、短時間でもよいので日光に当たる習慣を取り入れてみましょう。
3-3. ストレスを我慢して抱え込む
責任感が強く、真面目な人ほど「弱音を吐くのは甘え」「誰かに迷惑をかけたくない」と、我慢をしてしまいがちです。
しかし、感情を抑え続けると、自律神経が乱れて心も体も緊張状態が続きます。交感神経が優位なままだと、眠ってもリラックスできず、疲労が溜まります。
ストレスを溜め込まないためには、気持ちを外に出すことが大切です。信頼できる人に話すのはもちろん、紙やノートに書き出すだけでも、気持ちが整理されて落ちつきやすくなるでしょう。
疲れやすい体質を変える!すぐにはじめられる5つの改善法

「なんとなくだるい」「気力が出ない」とお悩みの方に向けて、今日からでもすぐはじめられる5つの対処法をご紹介します。
無理なく取り入れやすい方法ばかりなので、自分に合ったものからはじめてみてください。
4-1. 疲れに効く食べ物を積極的に摂る
疲れやすい方は、体を動かすエネルギーや、代謝に必要な栄養素が足りていない可能性があります。
| <疲労回復に役立つ栄養素> | ||
| 栄養素 | 働き | 食材の例 |
| ビタミンB群 | 糖質や脂質をエネルギーに変える | 豚肉、卵、納豆 |
| クエン酸 | 疲労物質を分解する | レモン、梅干し、酢 |
| タンパク質 | 筋肉の材料であり、体力維持に役立つ | 魚、鶏むね肉、大豆製品 |
| 鉄 | 体中の細胞に酸素を運ぶ | レバー、赤身肉、ほうれんそう |
疲れにくい体をつくるためには、バランスのよい食事を心がけ、疲れに効く栄養素を積極的に取り入れてみてください。
疲れていて食欲がわかない場合は、スープやおかゆといった消化にやさしいものから、少しずつ体にエネルギーを届けるようにしましょう。
4-2. 軽めの運動や筋トレを習慣化する
疲れにくい身体をつくるには、日々の生活に軽めの運動や筋トレを取り入れることが効果的です。
ウォーキングやストレッチといった運動は、血行を促進して疲労物質を排出しやすくするほか、気分をリフレッシュさせてストレスもやわらげてくれます。
激しい運動を無理にする必要はなく、朝の散歩や、エレベーターではなく階段を使うなど、日常に取り入れやすい工夫で十分です。無理なくできる運動習慣を継続してみましょう。
4-3. 湯船に浸かる
毎日の疲れを癒すには、シャワーだけで済ませず、湯船にゆっくり浸かることが効果的です。ぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かることで、血行が促進され、筋肉の緊張もほぐれます。
また、副交感神経が優位になることで心が落ち着き、寝つきがよくなる効果も期待できます。熱すぎるお湯や長風呂は、かえって体力を奪ってしまうので、38〜40℃程度のぬるめのお湯での入浴がおすすめです。
4-4. ツボを押す
日常のなかで簡単にできるセルフケアとして、ツボ押しもおすすめです。
<疲れにおすすめのツボ>
- 労宮(ろうきゅう):手のひら中央、指を軽く曲げたとき中指が触れる位置にあるツボ
- 足三里(あしさんり):膝のお皿の下、外側に指4本分下がったところにあるツボ
テレビを見ているときや、寝る前のリラックスタイムなど、スキマ時間にぜひ実践してみてください。
4-5. サプリメントや漢方薬を活用する
健康で疲れにくい身体づくりのためには、栄養バランスの整った食生活が理想的です。しかし、仕事や家事、育児で忙しいと、なかなか食事に気をつかえないこともあります。
そんなときは、ビタミンB群や鉄といった、疲労回復に役立つ栄養素をサプリメントで補うのもおすすめです。
疲れにくい体質を目指すためには、医師や薬剤師と相談したうえで、自身の体質や症状に合った漢方薬を活用する方法もあります。
疲労回復サプリどれを選べばいいか?疲労の原因別おすすめサプリについて専門家が解説 >>
疲れ対策には複合成分を含むサプリメントもおすすめ

疲れやすい体質にお悩みの方のなかには、日ごろからサプリメントを取り入れている人もいるかもしれません。
しかし、疲れの原因がホルモンバランスの乱れや栄養不足、自律神経の不調などの複数の要素から成り立っている場合、単一成分のサプリメントだけでは十分な効果を感じにくいこともあります。
疲れやだるさといった、病名のつかない不調(未病)の対策で重要なのは、身体全体の自然治癒力を高めることです。そこで注目されているのが、漢方由来の成分を含んだ複合サプリメントです。
漢方や和漢ハーブをベースにしたサプリメントは、身体本来の自然治癒力を引き出し、元気を取り戻すためのサポートをしてくれます。
日頃の食生活を整えたうえで、体質に合った漢方由来の成分を取り入れると、慢性的な疲れに対して根本からアプローチできるでしょう。
疲れやすい体質に関するよくある質問
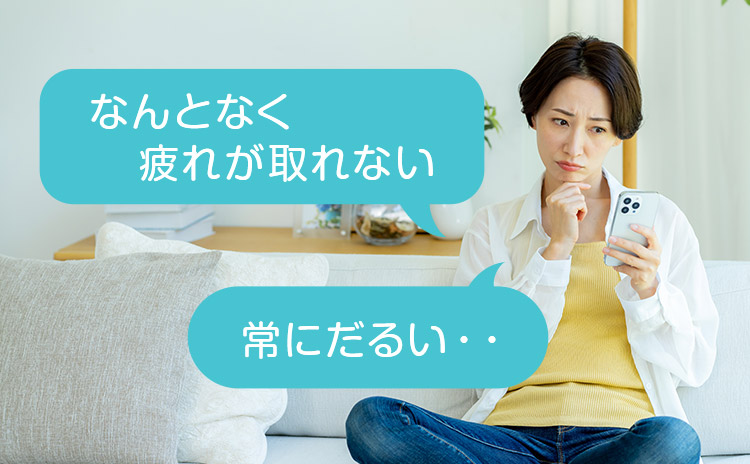
ここからは、疲れやすい体質に関するよくある質問について回答します。
6-1. 20代で疲れやすくなる原因には何がありますか?
20代でも、「なんとなく疲れが取れない」「常にだるい」と感じる方は少なくありません。
その背景には、慢性的なストレスや睡眠不足、偏った食生活、運動不足などが関係していることが多くあります。
とくに現代の若い世代に見られるのが、スマートフォンやパソコンの長時間使用による「眼精疲労」や、マルチタスクや過労などによって起こる「脳疲労」です。
定期的に「デジタルデトックス」の時間を取ったり、意識的に目を休めたりして、疲れを溜めないように工夫しましょう。
6-2. 疲れにくい身体にするにはどうしたらいいですか?
基本的なことにはなりますが、疲れにくい身体づくりには、栄養バランスのとれた食生活や運動習慣、睡眠時間の確保などが重要です。この記事で紹介した、疲れに対する対処法をぜひ試してみてください。
また、ストレスも疲れやすさにつながるため、ストレス源からなるべく離れることや、自分に合ったストレス解消法をもつことも重要です。
6-3. 疲れやすい体質は生まれつきですか?
体質は遺伝する可能性もありますが、疲れやすさは日々の生活習慣も大きく関係しています。そのため、毎日の食事や運動、睡眠、ストレスケアなどを少しずつ見直していくことで、疲れにくい体に近づける可能性があります。
まずは生活習慣を見直し、それでも改善が見られない・悪化するといった状況であれば、何か病気が隠れている可能性もあるため、医療機関に相談するとよいでしょう。
まとめ
40代を迎えると、疲れが取れにくくなったり、気力や体力が落ちてきたりと、若いころとは異なる不調を感じる方が増えてきます。その原因は、ホルモンバランスの変化や筋力の低下、ストレスの蓄積などさまざまです。
疲れやすさは、食事や運動、睡眠、ストレスケアといった毎日の小さな習慣の積み重ねで、少しずつ改善できます。また、日々のセルフケアに加えて、漢方由来のサプリメントなどを活用し、疲れにくい身体づくりをするのもおすすめです。
無理のないペースで自分の身体と向き合いながら、今よりもっと元気に過ごせる毎日を目指していきましょう。