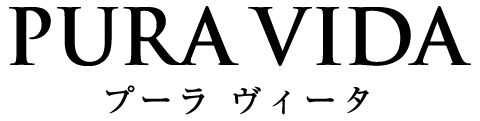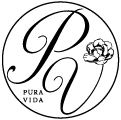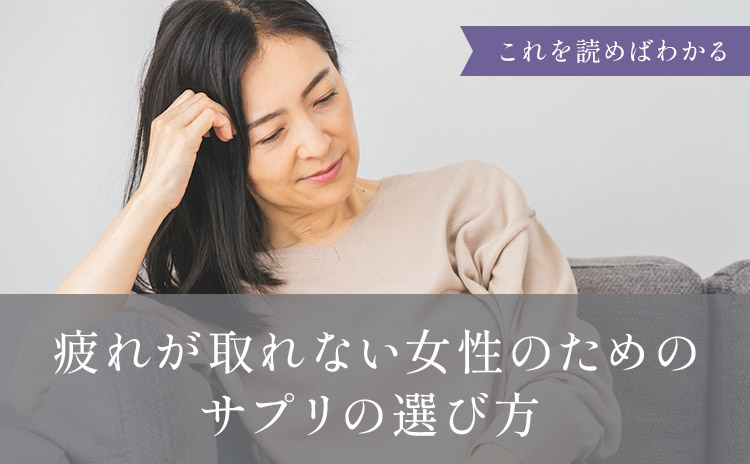「最近ずっと体が重くて、朝から動くのがしんどい…」
「だるさが抜けないのは年のせい?」
そのように悩んでいませんか?
体の重さやだるさは、睡眠不足や栄養の偏り、ストレスなどが主な原因として考えられます。
放置すると集中力や免疫力の低下につながり、日常生活や仕事にも影響を及ぼす可能性も否めません。
そこでこの記事では、以下の内容について解説します。
| この記事でわかること |
|
毎日をスッキリ過ごすためのヒントを、ぜひ参考にしてください。
目次
「体が重い、だるい」とはどういう状態?
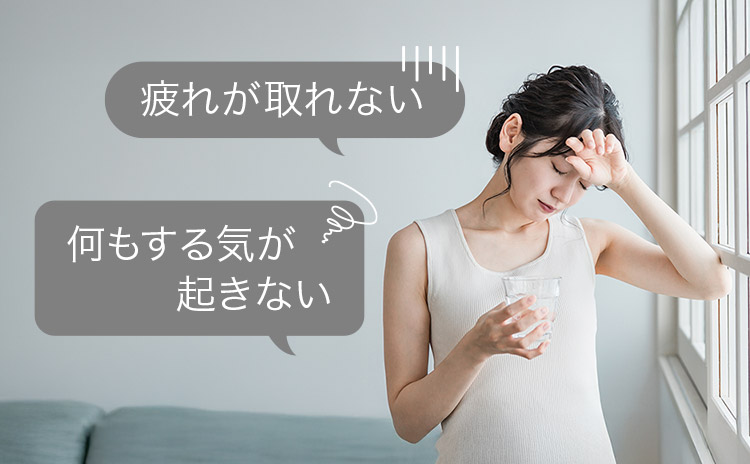
「体が重い、だるい」という感覚は、医学的には「倦怠感」と呼ばれます。
これは単なる疲労感にとどまらず、「疲れが取れない」「何もする気が起きない」といった心身の不調を伴う状態です。
原因としては、肉体疲労の蓄積や精神的ストレス、睡眠不足、運動不足などが挙げられ、生活習慣や心身の健康状態が大きく関係しています。
本来、体は恒常性と呼ばれる仕組みによって健康を保ちますが、倦怠感はそのバランスが崩れかけている危険信号の一つとされています。
通常であれば十分な休息で回復しますが、休んでも改善しない場合は病的な倦怠感の可能性があり、注意が必要です。
体が重い、だるいと感じる3つの原因
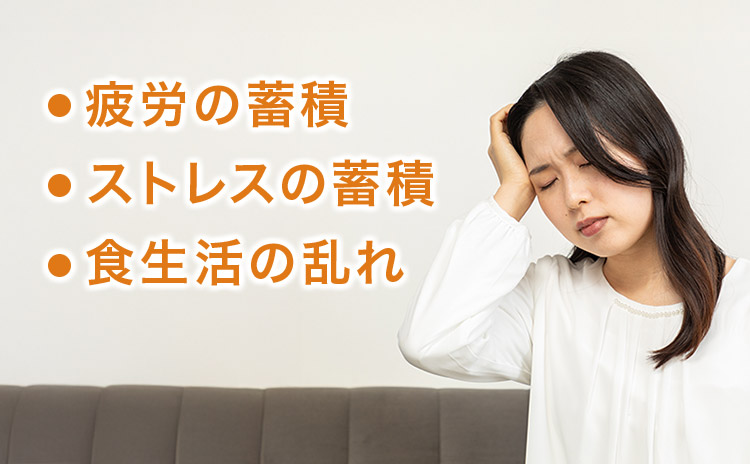
体が重い、だるいと感じる3つの原因として、以下が挙げられます。
- 疲労の蓄積
- ストレスの蓄積
- 食生活の乱れ
当てはまるものがないか、セルフチェックしてみましょう。
2-1. 疲労の蓄積
長時間の労働や睡眠不足、不規則な生活習慣は、肉体的・精神的な疲労を十分に回復させないまま蓄積させてしまいます。
この慢性的な疲労は体のだるさだけでなく、睡眠障害や集中力の低下など、多くの不調を引き起こしかねません。さらに、自律神経の乱れや血行不良を招き、体は強い休息の必要性を訴えるようになります。
回復が追いつかない状態が続くと、単なる休み不足を超えて、より深刻な健康トラブルに発展する恐れもあるため、早めの対策が重要です。
疲労回復術は、以下の記事を参考にしてみてください。
【医師監修】もう疲れない!今日からできる簡単疲労回復術 >>
2-2. ストレスの蓄積
仕事や人間関係、環境の変化による精神的ストレスは、自律神経のバランスを崩す大きな要因です。自律神経が乱れると、体のオン・オフの切り替えがうまくいかず、疲労回復力が低下してだるさや不眠を招きます。
| 参考: | 心と身体がしんどい原因は、自律神経?!-済生会 |
ストレスは体のエネルギーを消耗させるため、十分な休息をとっても疲れが取れない感覚に陥ることもあります。
この状態を放置すれば、うつ病など精神的な不調に発展する危険性もあり、ストレス対策は早めに行うことが重要です。
2-3. 食生活の乱れ
食事を抜いたり偏食を続けたりすると、体を動かすエネルギーが不足し、だるさを感じやすくなります。
炭水化物・タンパク質・脂質に加え、それらをエネルギーに変えるビタミンやミネラルが不足すれば、細胞の働きが低下しかねません。
特に鉄分不足による貧血は全身への酸素供給を妨げ、だるさや息切れの原因となります。
また、ストレス解消のためのやけ食いや過食は消化に負担をかけ、栄養バランスを崩してだるさを悪化させるため、注意が必要です。
鉄分不足を解消するためには、以下の記事をぜひ参考にしてみてください。
鉄分を美味しく摂取できる食べ物とは 女性の貧血対処レシピ 管理栄養士が伝授 >>
体が重い、だるいという状態を放置する3つのリスク
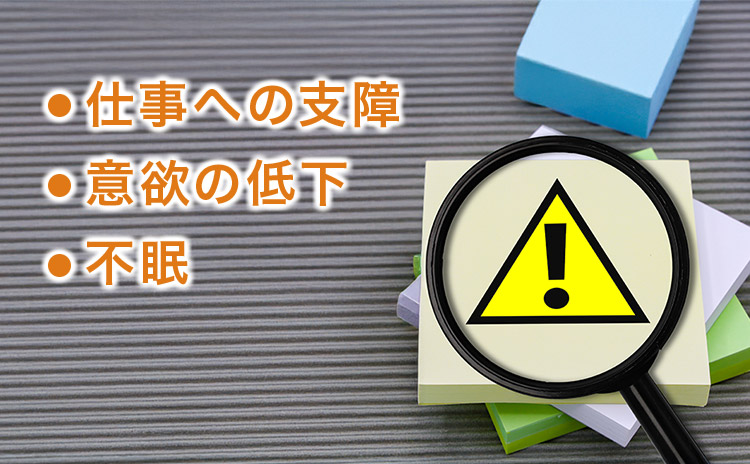
体が重い、だるいという状態を放置するのは、以下の観点からおすすめできません。
- 仕事に支障が出る
- 物事に対する意欲が下がる
- 不眠につながりやすくなる
それぞれ詳しくチェックしていきましょう。
3-1. 仕事に支障が出る
体が重く、だるい状態を放置すると、集中力や注意力が低下し、仕事上のミスや効率の悪化につながります。
疲労が蓄積すると、日中に強い眠気に襲われたり、思考力が鈍ったりして、普段なら難なくこなせる業務も困難に感じるようになるでしょう。
この状態が長引けば、遅刻や欠勤の増加など、日常生活そのものにも影響が及びます。
だるさは単なる疲れではなく、仕事のパフォーマンスを大きく損なう危険信号であり、早期の改善が不可欠です。
3-2. 物事に対する意欲が下がる
慢性的なだるさは、身体だけでなく心のエネルギーも奪い、無気力な状態を引き起こします。
以前は楽しめていた趣味や活動にも興味が持てなくなり、「やりたい」という気持ちが湧かなくなることも少なくありません。
この意欲の低下は、心身のエネルギーが枯渇しているサインであり、うつ病など精神疾患の初期症状である可能性もあります。
さらに悪化すると、日常生活における簡単な決断すら難しくなり、社会生活への参加が困難になることも想定されるでしょう。
3-3. 不眠につながりやすくなる
だるさを放置すると、「疲れているのに眠れない」という矛盾した状態に陥ることがあります。
これはストレスや自律神経の乱れによって心身が緊張状態から抜け出せず、寝つきの悪化や夜間の中途覚醒など、睡眠の質が著しく低下するためです。
十分な睡眠が取れないと脳と体の回復が妨げられ、翌日のさらなるだるさや意欲低下を招く悪循環が生まれます。
睡眠障害はうつ病などの精神疾患とも深く関係しており、早期の対応が必要です。
不眠に悩んでいる方は、ぜひこちらの記事もチェックしてみてください。
【医師監修】寝ても寝ても眠いのはなぜ?原因と対処法を詳しく解説 >>
体が重い、だるいと感じる際の5つの対策

体が重い、だるいと感じる際の5つの対策として、以下がおすすめです。
- 生活習慣を見直す
- 運動する習慣を作る
- 質の高い睡眠を確保する
- バランスの取れた食事を行う
- 正しい入浴を心がける
いずれも取り組みやすいものばかりなので、生活に早速取り入れてみましょう。
4-1. 生活習慣を見直す
体のだるさを解消するためには、まず生活リズムを整えることが基本です。不規則な生活は自律神経を乱し、疲労を蓄積させる原因となります。
食事、睡眠、運動など、乱れている部分があれば改善する習慣を持ちましょう。
また、ストレスも自律神経に大きく影響するため、自分に合ったリフレッシュ方法を見つけ、心身を休める時間を意識的に確保することが大切です。
4-2. 運動する習慣を作る
軽い運動は血行を促進し、倦怠感の改善に効果的です。特にウォーキングやラジオ体操などの一定リズムで行う「リズム運動」は、心身のバランスを整えやすくなります。
長時間の激しい運動は必要なく、短時間でも毎日続けられる内容を選ぶことがポイントです。
運動は気分転換やストレス解消にもつながり、だるさ対策として継続的な効果が期待できます。
自宅で取り組みやすいトレーニングは、以下の記事で解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
痩せやすい体を作る自宅でできるトレーニング。ボディメイクのスペシャリストが伝授します。 >>
4-3. 質の高い睡眠を確保する
疲労回復には、十分な睡眠が欠かせません。目安として7時間以上が推奨されますが、重要なのは朝すっきり起きられる自分に合った睡眠時間を見つけることです。
寝る前に40℃以下のぬるめの湯船に浸かるとリラックスしやすく、寝つきも良くなります。
また、ブルーライトは脳を覚醒させるため、就寝1時間前にはスマホやPCの使用を控えましょう。
以下の記事もチェックして、睡眠に関する理解度を深めてみてください。
知っているようで知らない「睡眠の質」の重要性。睡眠の質を上げる秘訣を専門家が解説 >>
4-4. バランスの取れた食事を行う
栄養バランスの乱れは、体のだるさへとつながりかねません。
糖質・脂質・タンパク質といったエネルギー源に加え、それらの代謝を助けるビタミンやミネラルをバランス良く摂取することが大切です。
特に鉄分は酸素を全身に運び、疲労感を軽減する役割があるため、以下の表を参考に摂取してみてください。
| 鉄分を多く含む食品 | 鉄分量 |
| 豚レバー | 約13mg |
| あさり(水煮缶) | 約11mg |
| ひじき(乾燥) | 約6.2mg |
| 納豆 | 約3.3mg |
4-5. 正しい入浴を心がける
入浴は血行を促進し、筋肉の緊張をほぐすことで疲労物質の排出を助けます。40℃以下のぬるめのお湯に10〜30分ゆっくり浸かると、副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに切り替わりやすくなるでしょう。
一方、熱すぎるお湯は交感神経を刺激し、かえって緊張や不眠の原因になることがあるため注意が必要です。温度調整をした上で入浴する習慣を身につけましょう。
疲労回復術に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。
【医師監修】もう疲れない!今日からできる簡単疲労回復術 >>
体が重い、だるいと感じる際によくある質問2選

体が重い、だるいと感じる際によくある質問2選として、以下をピックアップしました。
- 体が重い、だるいという症状が治らない時はどうすればいい?
- 熱はないのに体がだるくなる時があるのはなぜ?
それぞれどのような内容なのか、詳しく見ていきましょう。
5-1. 体が重い、だるいという症状が治らない時はどうすればいい?
十分な休養や生活習慣の見直しを行っても、だるさが1か月以上続く場合や動けないほどの強い疲労感がある場合は、単なる疲れではなく病気が隠れている可能性があります。
発熱や息苦しさ、吐き気など他の症状を伴う場合や、健康診断で血糖値や肝機能、ヘモグロビン値などに異常を指摘された場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
考えられる疾患には、貧血、糖尿病、甲状腺機能異常、肝臓・腎臓の病気、心不全、睡眠時無呼吸症候群、うつ病などがあります。
まずは内科や総合診療科を受診し、必要に応じて専門医につなげてもらうことが大切です。
疲れが取れない30代~50代の女性の方は、こちらの記事もチェックしてみてください。
疲れが取れない30代40代50代の女性。その原因と対処法 >>
5-2. 熱はないのに体がだるくなる時があるのはなぜ?
発熱がないのに慢性的なだるさを感じる場合、もっとも多い原因の一つがストレスや不規則な生活による自律神経の乱れです。
自律神経は体の活動と休息のバランスを司っており、乱れると十分に休めず、常にだるさを感じるようになります。
また、貧血も発熱を伴わない倦怠感の代表的な要因です。
さらに、糖尿病や甲状腺疾患、肝機能の低下、うつ病などの精神疾患も、初期症状として熱のないだるさを引き起こすことがあります。
このため、症状が長引く場合は早期の受診が重要です。
体が重い、だるいという症状が続くときはサプリメントを試してみよう

日常的な疲労感がなかなか取れない場合は、生活習慣の改善に加えてサプリメントの活用も有効です。
特に、東洋医学の知恵を取り入れた和漢サプリメントは、自然由来の成分で体のバランスを整えながら疲労回復をサポートしてくれます。
有機マカや田七人参は、エネルギー代謝を高め、持続的な活力を引き出す成分として知られています。さらに、ウコンに含まれるクルクミンは抗酸化作用や代謝促進作用があり、体内環境の改善に役立ちます。
サプリメントの効果を実感しやすくするには、毎日続けるのがおすすめです。特に朝食後に取り入れることで、その日一日のエネルギー補給効率が向上します。
また、着色料・保存料・香料無添加の和漢サプリメントを選べば、安心して続けられる点も魅力です。
定期的な運動や質の高い睡眠と組み合わせることで、回復効果はさらに高まります。
日々の生活で蓄積された疲れをやわらげ、活力ある毎日をサポートするためにも、こうした自然由来の成分を取り入れたサプリメントを上手に活用してみましょう。
なお、疲労回復サプリに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
疲労回復サプリどれを選べばいいか?疲労の原因別おすすめサプリについて専門家が解説 >>
まとめ
「体が重い、だるい」とは、医学的には「倦怠感」と呼ばれ、単なる疲労感以上の心身不調を伴っていることが多い傾向にあります。
疲労やストレスの蓄積、食生活の乱れによって引き起こされることが多いため、原因を見極めて対処することが重要です。
体の重さやだるさを放置していると、物事への意欲低下、仕事の支障、不眠などにつながりかねません。
生活や運動習慣を見直すことはもちろん、睡眠や入浴の改善で体が重い、だるいといった状態から抜け出しましょう。
有機マカ、田七人参、ウコンなどが入った和漢サプリメントであれば、体が重い、だるいといった状態から回復しやすくなります。
ぜひ普段の生活に取り入れ、体の重さやだるさを改善しましょう。