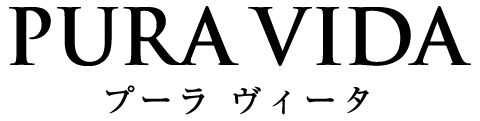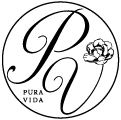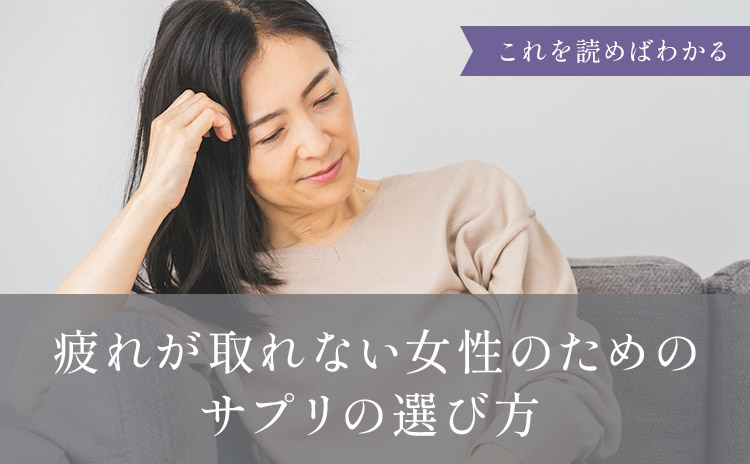「最近ずっと体がだるくて、朝起きるのもつらい…」
「何を食べれば本当に疲れが取れるのか知りたい」
日々の疲れがなかなか抜けないと感じている方は、もしかすると食生活に原因があるかもしれません。
この記事では解決策として、以下の内容を解説します。
| この記事でわかること |
|
どのように食事を見直せばいいか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
食べ物で疲労を回復させるための3つのポイント

食べ物で疲労を回復させるための3つのポイントとして、以下を押さえておきましょう。
- 栄養バランスを考える
- 三食しっかりと摂る
- 消化に良いものを選ぶ
なかなか体力が回復しないという方は、参考にしてみてください。
1-1. 栄養バランスを考える
食べ物で疲労を回復させるには、栄養バランスを考えることが重要です。
特に炭水化物、タンパク質、脂質の三大栄養素をしっかり摂りつつ、ビタミンやミネラルなどの栄養素も補給することで、栄養の吸収率が上がります。
また、主食、主菜、副菜、乳製品、果物の5つをバランスよく揃えることも大切です。
加工食品に偏ると栄養バランスが崩れ、疲労回復が遅れるため、注意してメニューを考えましょう。
1-2. 三食しっかりと摂る
一日三食をきちんと摂ることも、疲労回復の重要なポイントです。
食事を規則的に摂ることで体内のエネルギー不足を防ぎ、集中力や体力が回復しやすくなります。特にダイエット目的で食事を極端に減らすと、エネルギーが足りず、疲れやすくなります。
また、食事間隔が空きすぎると、次の食事後に血糖値が急激に上がるリスクもあるため、注意が必要です。
疲労回復、健康の観点から、三食をなるべく決まった時間に食べる習慣を身につけましょう。
1-3. 消化に良いものを選ぶ
疲れているときは消化機能も落ちていることが多いため、消化に良い食品を選びましょう。
メニューを考える際は、以下のリストを参考にしてみてください。
| 消化に良い食べ物のカテゴリー | 食品名 |
| 炭水化物 |
|
| タンパク質 |
|
| 野菜 |
|
| 果物 |
|
いずれの食品も栄養価が高いので、本当に疲れて食欲がないときなどにもおすすめです。
疲労回復につながる食べ物5選

疲労回復につながる食べ物5選として、以下をご紹介します。
- 肉類
- 魚類
- 穀類
- 卵
- 果物類
どのような食べ物があるのか見ていきましょう
2-1. 肉類
豚肉や鶏肉、牛肉などに豊富に含まれるタンパク質は、日々の活動で疲れた筋肉の修復を効果的にサポートしてくれるのがメリットです。
さらに肉類にはビタミンB群も多く含まれており、食べた炭水化物をエネルギーに変換する重要な働きを担っています。
また、肉類に含まれるアミノ酸は疲労物質の分解を促進する効果もあるため、疲れを溜め込みにくい体づくりに役立ちます。
2-2. 魚類
魚類に含まれるセレンという成分には強い抗酸化作用があり、疲労の原因となる活性酸素を除去する働きがあるのが特長です。
また、魚類の大きなメリットは消化吸収が良く、胃腸への負担が少ないこと。
疲れている時でも食べやすく、体に優しいのが嬉しいポイントです。
さんまやアジ、かつおなど、良質なタンパク質を含む魚類を積極的に食べましょう。
2-3. 穀類
パンや白米などに含まれる炭水化物は、体にとって最も効率の良いエネルギー源となり、即座に活力を与えてくれます。
また、穀類に含まれる食物繊維は腸内環境を整える効果があり、他の栄養素の吸収を助ける役割も担っています。
ただし、穀類の食べ過ぎは糖質過多になる可能性もあるため、他の栄養素を含む食材とのバランスも考えてメニューを組みましょう。
2-4. 卵
卵は「完全栄養食品」と呼ばれるほど栄養価が高く、疲労回復にも効果のある食材です。
必須アミノ酸がバランス良く含まれているだけでなく、鉄分やビタミンDなど多様な栄養素を一度に摂取できるのは、卵ならではの強みといえます。
また、卵に含まれるビタミンB群が代謝を活発にし、疲労回復のスピードを早めてくれる効果があるのも特徴です。
卵は調理方法も豊富で価格も手頃なため、毎日の食事に取り入れやすい優秀な食材といえるでしょう。
2-5. 果物類
レモンやいちご、ミカンなどに含まれる天然の糖分は体に素早く吸収され、即効性のあるエネルギー源となります。
特にビタミンCの豊富さは果物類の大きな特徴で、抗酸化作用により疲労の原因となる活性酸素を除去します。
さらに多くの果物に含まれるクエン酸は、疲労物質である乳酸の分解を促進し、疲労回復を早める働きがあります。
果物にはレモン、いちご、キウイなどさまざまな種類があるので、自分の好みから選びやすいのも嬉しいポイントです。
疲労回復におすすめな料理レシピ3選
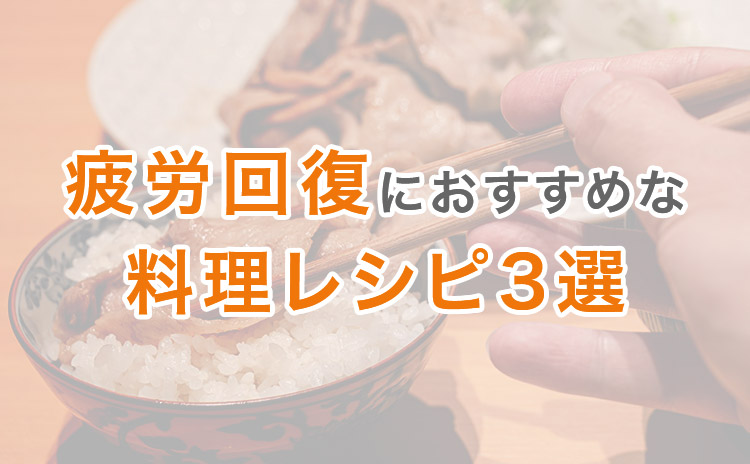
疲労回復におすすめな料理レシピ3選をご紹介します。
- 豚肉の生姜焼き
- レバニラ
- スペイン風オムレツ
いずれも手軽に再現できるメニューなので、ぜひ参考にしてみてください。
3-1. 豚肉の生姜焼き
豚肉に豊富に含まれるビタミンB1が、疲労物質(乳酸)の分解を助けてくれます。
特に仕事などで疲れた時に食べると、効果を実感できるスタミナ食です。
加えて、生姜の成分であるショウガオールが血行を促進し、身体を温めてくれるのも大きなメリット。体力向上はもちろん、風邪予防にも効果があります。
- 豚こま肉200gに、醤油大さじ2・みりん大さじ2・酒大さじ1・おろし生姜小さじ1を加えて混ぜる
- 玉ねぎ1/2個を薄切りにし、フライパンで軽く炒める
- 玉ねぎの上に下味をつけた豚肉を加え、中火で炒め合わせる
- 肉に火が通ったら火を止め、全体をよく混ぜて完成
3-2. レバニラ
レバーは鉄分やビタミンAやビタミンB群が豊富で、貧血や倦怠感に効果があります。日中、だるさやふらつきを感じることが多い場合、心強い味方となってくれるでしょう。
また、ニラにはアリシンが含まれ、血流を改善して代謝を助けてくれます。
レバニラを食べることで、タンパク質やミネラルも補えるため、全身の栄養補給が期待できるでしょう。
- レバー200gは薄切りにして水にさらし、臭みを取る
- ニラ1束は5cm幅に、もやし100gは軽く水洗いしておく
- レバーに片栗粉をまぶし、フライパンで炒めて一度取り出す
- 同じフライパンでもやしとニラをさっと炒め、レバーを戻す
- 醤油・酒・オイスターソース各大さじ1を加えて混ぜ、完成
3-3. スペイン風オムレツ
卵は良質なタンパク質とビタミンDを含み、体の修復に役立ちます。
エネルギー源としても優秀で、疲れた時の活力となってくれるでしょう。
また、玉ねぎに含まれる硫化アリルが、疲労物質の排出を促進します。
スペイン風オムレツを食べることで、効率良く体力回復につながります。
- じゃがいも1個と玉ねぎ1/2個を薄切りにして、オリーブオイルでじっくり炒める
- 卵3個をボウルに割り入れて溶き、炒めた具材を加えて混ぜる
- フライパンに油をひいて卵液を流し入れ、弱火でじっくり焼く
- 表面が半熟になったら裏返し、もう片面も焼く
- 両面がこんがり焼けたら火を止め、切り分けて完成
疲労回復に必須な栄養素5選

疲労回復に必須な栄養素として、以下の5つをピックアップして解説します。
- ビタミンB群
- タンパク質
- ビタミンC
- クエン酸
- 鉄分
実際にどのような効果があるのかチェックして、理解を深めていきましょう。
4-1. ビタミンB群
疲れがなかなか取れないという方は、ビタミンB群不足が原因かもしれません。
特にビタミンB1は、私たちが食べた炭水化物をエネルギーに変換する重要な役割を担っています。
| 参考: | 身体と心の疲労回復 – 高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
このビタミンB群が足りなくなると、体内に疲労物質である乳酸が溜まりやすくなり、慢性的な疲労感につながってしまうので、注意が必要です。
豚肉や鶏肉、魚類などの動物性食品に豊富に含まれているため、バランスの良い食事を心がけることで効率的に摂取できます。
4-2. タンパク質
体の疲労回復において、タンパク質は欠かせない栄養素の一つです。運動や日常生活で疲れた筋肉の修復を助けるだけでなく、免疫力の向上にも大きく貢献します。
タンパク質が不足してしまうと体力の低下を招き、些細なことでも疲れを感じやすくなってしまいます。
肉類や魚介類はもちろん、大豆製品や卵、乳製品からも良質なタンパク質を摂取することが可能です。
時間がない場合、プロテインバーやナッツ類を間食として取り入れるのもおすすめの方法といえるでしょう。
4-3. ビタミンC
ビタミンCの持つ抗酸化作用は、疲労回復において非常に重要な働きをしています。
日々のストレスや紫外線などによって体内に発生する活性酸素を除去し、疲労の蓄積を防いでくれるのがポイントです。
また、鉄分の吸収を促進する効果もあり、全身への酸素供給をスムーズにします。
さらに、疲労物質の分解を助ける働きもあるため、疲れにくい体づくりには必要不可欠な栄養素といえます。
レモンやオレンジ、キウイフルーツなどの果物に多く含まれているので、デザートやおやつとして積極的に取り入れてみましょう。
4-4. クエン酸
クエン酸は体内でエネルギー代謝を活発にし、疲労物質の除去をサポートする働きがある栄養素です。運動後の筋肉疲労に対して、その回復を早める効果が注目されています。
| 参考: | 各種有機酸類による疲労回復促進効果 – 信州大学 |
クエン酸は主に、レモンやグレープフルーツなどの柑橘類に豊富に含まれています。最近では、コンビニやスーパーでクエン酸入りのドリンクやサプリメントも手軽に購入できるようになりました。
運動習慣のある方や肉体労働をされている方は、まずはドリンクやサプリメントで摂取してみましょう。
4-5. 鉄分
鉄分は赤血球の主要成分であるヘモグロビンの材料となり、全身の細胞に酸素を運ぶ重要な役割を果たしています。
鉄分が不足すると酸素の運搬能力が低下し、運動能力の減退や慢性的な疲労感を引き起こしてしまいます。
レバーや赤身肉、魚類などに多く含まれているほか、最近では鉄分補給用のグミやサプリメントも登場しているのでおすすめです。
特に女性は月経などにより鉄分が不足しがちなので、意識的に摂取しましょう。
疲労につながる3つの原因

疲労につながる3つの原因として、以下を理解しておきましょう。
- 睡眠時間が足りていない
- 腸内環境に問題がある
- 病気の症状に関係がある
原因を理解したうえでどのようなアプローチをすればいいのか、把握しましょう。
5-1. 睡眠時間が足りていない
睡眠の質が悪いと、深い眠りである「ノンレム睡眠」の時間が減少し、成長ホルモンの分泌が低下を招きます。
その結果、体力回復を妨げ、慢性的な疲労感を引き起こす要因になりかねません。
睡眠の質が悪い場合は、睡眠環境の早急な改善が必要です。
睡眠時間が短く、質も悪いと、将来の健康状態に関わることが明らかにされています。
また、不規則な睡眠パターンは体内時計を乱し、疲労感を増幅させる原因となってしまうため、併せて注意しましょう。
5-2. 腸内環境に問題がある
腸内細菌のバランスが崩れると、栄養素の吸収効率が低下し、慢性的な疲労を引き起こしやすくなります。
特に偏った栄養バランスの食事を続けていると、腸内細菌のバランスが崩れやすくなるので注意が必要です。
また、ストレスは腸のぜん動運動を乱し、消化不良や栄養吸収の低下を招くため、定期的なストレス発散も行いましょう。
意外と見落としがちですが、腸内環境も疲労に大きく関係するので、意識して改善することが大切です。
腸内環境が悪いときに現れる5つの症状!原因や整えるための改善策も紹介 >>
5-3. 病気の症状に関係がある
さまざまな改善方法を試しても、改善の兆しがない場合は何かしらの病気を患っているリスクがあるかもしれません。
疲労につながりやすくなる代表的な病は以下の通りです。
| 病名 | 疲労の原因 |
| 甲状腺機能低下症 | 甲状腺ホルモンの分泌が減少 |
| 糖尿病 | 血糖値の変動 |
| 慢性疲労症候群 | 免疫や神経系の異常 |
あくまでも代表例ですが、多くの改善方法を試しても疲労回復が見込めない場合は、これらの病気の疑いがないか医療機関の受診を検討しましょう。
食べ物以外で疲労回復する3つの行動

食べ物以外で疲労回復する3つの行動として、以下をおすすめします。
- 軽度の有酸素運動を続ける
- 6時間以上8時間未満の睡眠を取るようにする
- 湯船に浸かる習慣を作る
どのように実施すればいいのか、1つずつ見ていきましょう。
6-1. 軽度の有酸素運動を続ける
軽いジョギングやウォーキングなどの有酸素運動は血流を促進し、疲労物質や老廃物の排出をサポートしてくれるので、継続することが大切です。
休日に有酸素運動を続けることで、ただ身体を休めるよりも効率よく疲労回復につながります。
運動強度は息がはずみながらも会話ができる程度が適切で、週2~3回程度の頻度が理想的です。
初心者でも取り組める軽度の有酸素運動として、以下が挙げられるので、ぜひ実践してみましょう。
| 運動の種類 | メリット |
| ウォーキング |
|
| ジョギング |
|
| サイクリング |
|
6-2. 6時間以上8時間未満の睡眠を取るようにする
睡眠は疲労回復に最も重要な要素で、必要な睡眠時間は6時間以上8時間未満とされています。
個人差はありますが、十分な睡眠時間が取れれば、脳と体の両方の疲労を効率よく回復できるでしょう。
一方で寝不足が続くと、疲労回復につながらず、仕事のパフォーマンスも低下しやすくなります。
夜更かしを避け、毎日6時間以上8時間未満の睡眠時間を確保するように努めましょう。
知っているようで知らない「睡眠の質」の重要性。睡眠の質を上げる秘訣を専門家が解説 >>
6-3. 湯船に浸かる習慣を作る
湯船に浸かることで、血行が促進され、疲労物質が排出されやすくなります。
効果を十分に出すためにも、40℃程度のぬるめのお湯に10~15分程度全身浸かることが大切です。
実際にシャワーのみの入浴と比較して、湯船に浸かることで「熟睡感」「身体疲労感の回復・解消」「身体の軽快感」に好影響が出たという研究もあります。
| 参考: | シャワー浴からバスタブ浴への行動変容が睡眠と作業効率に及ぼす効果について -J-STAGE |
就寝の1時間半前を目安に入浴することで、眠りも深くなるので意識して続けてみましょう。
疲労回復を実現したいのであれば漢方由来のサプリメントがおすすめ!
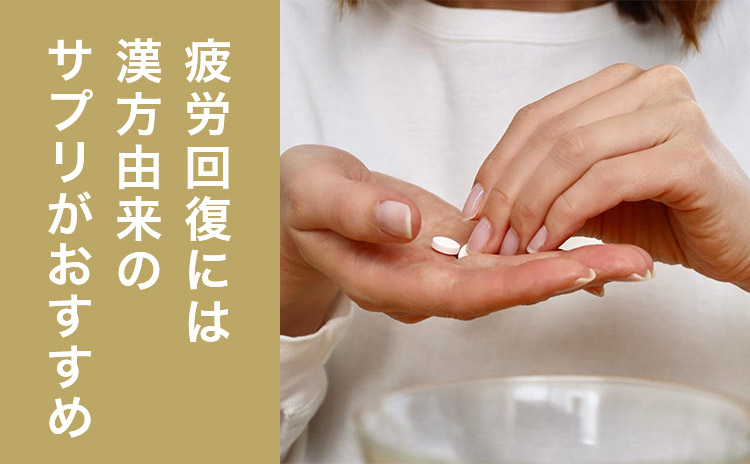
体の疲れには、だるさや頭痛、月経不順、不眠など、さまざまな原因があります。
こうした複合的な原因が絡む疲れの場合、特定の成分だけのサプリメントを使っても、根本的な解決にはつながらないことがあります。
そこでおすすめなのが、自然治癒力を高めるために、漢方由来の成分を含んだサプリメントを継続的に取り入れることです。
漢方(伝統生薬)は、身体を部分ではなく全体として捉える東洋医学の考え方に基づいており、本来備わっている回復力を引き出す手助けをしてくれます。
特定の症状にとどまらず、心と体のバランスを整えることで体質の改善を実現しやすくなるため、疲れにくい体を目指すことができるでしょう。
「仕事のパフォーマンス向上のためにもしっかりと疲れを取りたい」「一般的なサプリでは効果が出ない」と感じている方は、漢方由来の成分を配合したサプリメントをぜひ試してみてください。
【セルフチェック付き】疲れが取れない40代女性はどのサプリを選べばいいか。専門家が解説 >>
疲労回復サプリどれを選べばいいか?疲労の原因別おすすめサプリについて専門家が解説 >>
まとめ
食べ物で疲労を回復させるためには、炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラルなどの栄養素をバランス良く摂ることが大切です。
今回ご紹介した「豚肉の生姜焼き」「レバニラ」「スペイン風オムレツ」はこれらの栄養素を取り入れやすいメニューなので、ぜひ試してみてください。
もし食事にまで気を配れない場合は、漢方由来のサプリメントを摂取することもおすすめです。自分のできる範囲で、疲労回復のための行動を進めていきましょう。